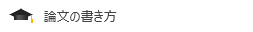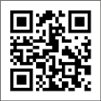資料紹介
中央大学2009年課題
 All rights reserved.
All rights reserved.
資料の原本内容
不動産取引は、当事者間では意思表示のみによって効力を生ずる(民法176条)。しかし、第三者に対する関係では、その登記をしなければこれを第三者に対抗することができない(民法177条)。例えば、BがAからその所有する不動産を購入した場合であるが、AB間(当事者間)では合意のみで所有権移転の効力が生ずる。しかし、第三者Cに対してBが所有権を取得したことを主張するためにはBはその登記をしておかなければならない。要するに、日本の民法は、登記を不動産物権変動の成立要件とはせずに、第三者に対する対抗要件としている。
登記の効力には、対抗要件のほかに公信力(公示を信頼した者の信頼を保護する公示の力)がある。日本民法は、動産の占有には公信力を認めたが、不動産の登記には公信力を認めなかったのである(判例・通説)。そのため、第三者が登記を信頼して取引をしても、その登記に伴う実体的な権利が存在しない場合、第三者は保護されない。日本における不動産取引は、善意の第三者の保護よりも真の権利者の保護の方が重視されたためである。今日では、この不動産登記に公信力が認められていないことから、不動産登記の信頼性は低いとも考えることができるが、民法94条2項に基づく通謀虚偽表示や、民法110条に基づく表見代理の制度などにより、結果的に登記に公信力を認めたことと同様の効果を与える取扱いが、実務上ではなされている。
不動産物権変動の対抗要件であるが、典型的な例として、二重売買がある。AがBに不動産を売買し、Bが登記をしていないうちに、さらに、Aは同一の不動産をCに売買し、Cが先にAから移転登記を得た。この場合、不動産の所有権はBとCのどちらに帰属するか。177条の適用の結果、移転登記を得ている第二譲受人のCがBに勝つ。第三者の関係においては、物権変動の時期の前後にかかわらず、先に登記した者が勝つ(対抗要件主義)。
対抗要件主義の目的は、公示の原則の要請であるが、第二譲受人を優先させる結果の合理性を支える思想とは、登記をすることができる状態にあるにもかかわらず、それをしなかった者は、不利益を受けても仕方がないとう登記の懈怠(怠慢)という帰責性である。
対抗要件主義は、不動産の権利関係のすべてをできる限り登記に反映させることを意図していた。しかし、今日では、不動産利用権との関係で、この対抗要件主義の原則に対して大きな修正が加えられている。例えば、建物所有を目的とする地上権や賃借権は、それ自体の登記がなくても地上権者・賃借権者がその土地上に登記した建物を所有する時、その地上権・賃借権を第三者に対抗できる(旧建物保護法1条・借地借家法10条)。また、借家については、その賃借権の登記がなくても、建物の引渡しがあった時、第三者に対抗できる(旧借家法1条・借地借家法31条)。
不動産物権変動の対抗要件主義を定めた177条の適用であるが、次の2点の解釈が問題とされている。第1に、177条にいう第三者の範囲であり、第2に177条が適用される物権変動原因の範囲である。第三者の範囲には、すべての第三者であるとする無制限説と範囲に制限があるとする制限説がある。
判例においては、当事者以外のすべての第三者に対して登記が必要であるという立場をとっていた(無制限説)。この説の背後には、不動産の取引の安全をはかるためには、登記による画一的処理が望ましいという登記中心主義の考えがあった。しかし、明治41年の大審院連合判決により、無制限説の立場を改め、177条にいう第三者は「登記の欠けんを主張する正当の利益を有する者」に限るとした(制限説)。登記なくして対抗できる者には、(1)正当な権原によらないで権利を主張する者(無権利者)、(2)不法行為者がある。このような者では、相手方に登記が欠けていることを主張できない。
学説においても、第三者に何らかの制限を加えることを認める点で、制限説が通説となっている。(1)当該不動産に関して有効な取引関係に立てる第三者ないし物権変動につき正当な取引関係に立つ第三者と解する。(2)第三者とは、対抗関係に立つ者のみであり、それ以外の者は第三者ではないと解する。
物権変動があったことを知る第三者(悪意の第三者)に対しても、登記がなければ物権変動を対抗することができないであろうか。判例・通説は、悪意者も177条の第三者であると解している(最判昭30・5・31)。理由としては、第1に、に177条の文言が第三者を善意者に限定していない。第2に、不動産取引はできるだけ登記を基準として画一的解決をはかった方が良い。すなわち、善意を必要とすれば、その立証をめぐる問題が起き、登記制度の目的である取引の安全が害されかねない。さらに、近時では、第3に、自由競争の原理が理由とされることがある。これに対して、悪意者排除説、善意かつ無重過失に限る説、善意・無過失を要求する説などの悪意者は保護に値しないとする考えもある。
どのような悪意者も177条によって保護されるのであろうか。極端に悪質・背信的である悪意者(背信的悪意者)を売買があることを知っていただけの悪意者と同様に保護することはできない。判例・通説においても背信的悪意者として177条の第三者から排除する理論が今日では確立している(最判昭44・1・16)。よって、登記なき第三者でも背信的悪意者に対抗できると言える。
この背信的悪意者から転得者がいる場合においては、転得者自身が背信的悪意者と評価されない限り、その不動産の所有権取得を第1譲受人に対抗できる(最判平8・10・29)。これに対して、転得者が背信的悪意者である場合は、背信的悪意排除論は相対的適用されるべきものであり、善意者の中間取得者の介在によって背信的悪意者は遮断されないとしている。
以上、不動産物権変動の対抗要件の177条の解釈を中心に論じた。177条解釈における問題には、第三者の範囲と物権変動原因の範囲の問題が挙げられる。第三者の範囲であるが、177条では、善意・悪意を区別していなく、悪意者も保護されるとすれば、悪意者からの譲受人も保護され、取引の安全に資する。悪意者は保護しないという見解もあるが、悪意者を保護しないということは、第三者が善意であるということを立証しなければならない。このような見解を支持するならば、その立証の方法は何であるかについても言及しなければならないと言える。
参考文献等
清水元『新・民法学2物権法』成文堂、33~61頁
尾崎哲夫『はじめての物権法』自由国民社、41~51頁
保留(レポに必要?)
次に、対抗問題として登記が必要とされるのは、すべての物権変動であるのか(無制限説)、それともその範囲に制限があるのか(制限説)が問題とされている。かつての判例にでは、意思表示による物権変動のみとし、制限説の立場をとっていた。しかし、その後の判例では、意思表示のみならず、一切の物権変動を含むと解するに至った(大連判明治41・12・15)。その理由としては、第1に、177条および不動産登記法3条にはこれを制限する文言がないこと、第2に、第三者の取引の安全のためには、それが意思表示に基づく物権変動かそれ以外の原因に基づく物権変動かを区別する理由がないことが挙げられる。
これに対して、意思表示による物権変動にかぎって対抗問題となると解する学説もある。これによれば、相続・取得時効などによる物権変動には177条は適用されないとする。
以上から、判例は基本的に、物権変動の種類を制限していなく、学説は、何らかの形で制限する方向だと言える。代表的なものとして取消のケースがある。法律行為は取り消されることがあり、取り消されるとその法律行為は最初から無効なものとみなされる。この問題と登記がからんだ場合、どのように処理すればよいであろうか。例えば、AがBを騙してBの家を1千万円で買い、その後、Cに1億円で売ってしまったとする。騙されたことを知ったBが売買契約を取り消した時、Bは登記がなくてもCに対抗できるであろうか。判例や従来の通説は、Bの取消がCへの売却の前か後かによって分けて考える。取消前にCに売られた場合は、Bは登記がなくても自分の土地の所有権をCに対抗できる。しかし、Cが善意・無過失ならば対抗できない。対して、取消後にCに売られた場合は、対抗できない。取消後は登記できるはずであり、それを怠っている者は対抗できなくなるということである。
民法2 第二課題
不動産取引においては、登記のみならず、善意・悪意または過失の有無を併せて考慮すべきであるとの見解を論評しなさい。