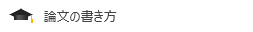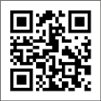資料紹介
江原由美子編 『フェミニズムとリベラリズム』
フェミニズムはリベラリズムの延長線上に位置するのか、それとも異なるものを求めるものなのか、本書はこの古くて新しい問題を正面から論じた論考を集めた、刺激的な一冊である。 リベラリズム、「自由主義」と通常訳される思想は、大まかには①個人主義,②改良主義,③公私二元論に基づく,④③を前提に公の領域での機会の平等と私の領域における個性の尊重と自由、を内容とする。そして、フェミニズムのある部分は、このような枠組みと重なり合う。女性解放としてのフェミニズムだけでなく、メンズリブやゲイ、トランスジェンダーなどのリベレーション運動についても同様である。
一方で、フェミニズムはリベラリズムを批判し、そのアンチテーゼを定立することによっても進展してきた。一方で、リベラリズムの提供する均質な個人像に対し、女性の生物学的・文化的本質を重視する立場が提唱されれば、他方で既存のリベラリズムが男性中心のものでしかないことを理由に、リベラリズムの徹底もしくは実質化、または逆にリベラリズム自体の脱構築を提唱する立場も現れた。
そのような中で議論自体は錯綜を深めているわけであるが、編者である江原由美子氏は、リベラリズムとフェミニズムの相剋を、「価値中立性と暗黙の価値前提をめぐる闘争」と捉える。すなわち、前者は性別を含め、個体の属性に拘わらず、あらゆる主体の均等を目指す。一方、後者は前者を、暗黙のうちに男性優位の価値観に捕らわれている点から、問題を掘り起こす。
むろん、リベラリズム自体はフェミニズムなどからの批判を受けながらも、例えば本書でも言及されている、「性の自己決定」にしても、今なおジェンダーに関する諸問題に鋭利な視点を投げかけていることは事実であろう。 しかし、この両者には、互いに相容れないものが存在していることも事実である。この点本書は、もとよりリベラリズムを一面的に肯定したり、否定したりというような浅薄な議論を避けつつ、フェミニズムとリベラリズムが織りなす位相のいくつかを示すものとして、評価されるべきものである。 * * * まず、岡野八代氏は、「リベラリズムの困難からフェミニズムへ」において、リベラリズムが看過してきたのは「身体を伴った、異なりを持った個人」の存在である、と指摘する。そして、この身体を持つ個人について扱うのが、フェミニズムであるとする。 すなわち、リベラリズムは、あたかも近代物理学が広がりのある物質を、重心のみからなる「質点」として扱ってきたように、自由意思に基づいて行動する個人を、抽象的理念として、身体のない点のように考え、その上での性別に関する平等を論じてきた。しかし、これは実は「すでに特定の身体的能力と特徴、社会的位置づけを前提としている」ものである。
これに対し、フェミニズムは、「身体をともなった一人ひとりのわたしたちの異なりが主要な関心」であるという。すなわち身体を、リベラリズムがそうするように私有すべき客体として見るのでもなく、ましてや自然として見るのでもなく、「社会化された身体」として捉える視点を提供してきた、という。つまり、「わたしの身体は、禁止や期待などの様々な社会的コードによって、あたかも『自然』であるかのように構成されている」ことを、明らかにしてきた、というのである。
そして、この身体の置かれている、外部的内部的環境を考慮しないがゆえ、リベラリズムは現状維持の思想に転化する、と批判する。 この点、リベラリズムに対し「身体」の項を持ち込むことは、下手を
タグ
 All rights reserved.
All rights reserved.
資料の原本内容
江原由美子編 『フェミニズムとリベラリズム』
フェミニズムはリベラリズムの延長線上に位置するのか、それとも異なるものを求めるものなのか、本書はこの古くて新しい問題を正面から論じた論考を集めた、刺激的な一冊である。 リベラリズム、「自由主義」と通常訳される思想は、大まかには①個人主義,②改良主義,③公私二元論に基づく,④③を前提に公の領域での機会の平等と私の領域における個性の尊重と自由、を内容とする。そして、フェミニズムのある部分は、このような枠組みと重なり合う。女性解放としてのフェミニズムだけでなく、メンズリブやゲイ、トランスジェンダーなどのリベレーション運動についても同様である。
一方で、フェミニズムはリベラリズムを批判し、そのアンチテーゼを定立することによっても進展してきた。一方で、リベラリズムの提供する均質な個人像に対し、女性の生物学的・文化的本質を重視する立場が提唱されれば、他方で既存のリベラリズムが男性中心のものでしかないことを理由に、リベラリズムの徹底もしくは実質化、または逆にリベラリズム自体の脱構築を提唱する立場も現れた。
そのような中で議論自体は錯綜を深めているわけであるが、編者である江原由美子氏は、リベラリズムとフェミニズムの相剋を、「価値中立性と暗黙の価値前提をめぐる闘争」と捉える。すなわち、前者は性別を含め、個体の属性に拘わらず、あらゆる主体の均等を目指す。一方、後者は前者を、暗黙のうちに男性優位の価値観に捕らわれている点から、問題を掘り起こす。
むろん、リベラリズム自体はフェミニズムなどからの批判を受けながらも、例えば本書でも言及されている、「性の自己決定」にしても、今なおジェンダーに関する諸問題に鋭利な視点を投げかけていることは事実であろう。 しかし、この両者には、互いに相容れないものが存在していることも事実である。この点本書は、もとよりリベラリズムを一面的に肯定したり、否定したりというような浅薄な議論を避けつつ、フェミニズムとリベラリズムが織りなす位相のいくつかを示すものとして、評価されるべきものである。 * * * まず、岡野八代氏は、「リベラリズムの困難からフェミニズムへ」において、リベラリズムが看過してきたのは「身体を伴った、異なりを持った個人」の存在である、と指摘する。そして、この身体を持つ個人について扱うのが、フェミニズムであるとする。 すなわち、リベラリズムは、あたかも近代物理学が広がりのある物質を、重心のみからなる「質点」として扱ってきたように、自由意思に基づいて行動する個人を、抽象的理念として、身体のない点のように考え、その上での性別に関する平等を論じてきた。しかし、これは実は「すでに特定の身体的能力と特徴、社会的位置づけを前提としている」ものである。
これに対し、フェミニズムは、「身体をともなった一人ひとりのわたしたちの異なりが主要な関心」であるという。すなわち身体を、リベラリズムがそうするように私有すべき客体として見るのでもなく、ましてや自然として見るのでもなく、「社会化された身体」として捉える視点を提供してきた、という。つまり、「わたしの身体は、禁止や期待などの様々な社会的コードによって、あたかも『自然』であるかのように構成されている」ことを、明らかにしてきた、というのである。
そして、この身体の置かれている、外部的内部的環境を考慮しないがゆえ、リベラリズムは現状維持の思想に転化する、と批判する。 この点、リベラリズムに対し「身体」の項を持ち込むことは、下手をすれば身体的差異に基づく本質主義に陥る。外性器や出産能力に根拠を置く古典的本質主義から、近年通俗的レベルにまで広がってきた脳の性分化説や、遺伝子・DNAに関する言説に至るまで、これらもまた確かに身体を論じてはいる。
しかし、岡野氏は、「身体」を、社会的な言説により構成されたものと捉えている。本文ではその具体的内容は明らかにされていないものの、身体を社会的なものと捉えることにより、フェミニズムとリベラリズムとの関係を再構築しようとしている。 すなわち、リアルな社会空間において、個々人の性別に基づく、あるいは性別カテゴリ内部の差異の捨象ではなく、それを前提とした上でなければ、真の自由と平等を獲得することは出来ないことを、主張しているのである。このことは、範例として引用されている同性愛者や障害者についても、並行してあてはまることであろう。もっとも、筆者がいうには、単に身体の差異を尊重します、というだけでは不十分であり、そこには社会的に意味づけられた身体の、精緻な分析が不可欠である、ということになる。 #評者(真樹子)による、狭義のトランスジェンダーと身体の問題 #についての考察を、後日アップします。 次に塩川信明氏の、「集団的抑圧と個人」は、旧ソビエト連邦の分析から、それぞれの「被抑圧集団」の定義と、個人との関係に注目する。 集団的抑圧、あるいは端的に差別と言ってもよいであろうが、を考えるときには、何らかの集団をカテゴライズされる。これは抑圧者の側から見て、当然のことであるが、アファーマティブ・アクションに代表されるように、抑圧を克服するための対応策についても、何らかの集団を措定せざるを得ない。さらに、心情面においても、「ブラック・イズ・ビューティフル」に代表されるように、弱者こそが集団を必要としている。
一方、この文脈で、「個人」の立場をとることは、それが抑圧者の立場であっても、被抑圧者の立場であっても、あるいは第三者的立場であっても、困難な選択であることを、塩川氏は指摘する。すなわち、抑圧者の立場に属する場合、被抑圧者からは「強者の側からの居直り」ととられる危険を常に冒さなければならない。一方、被抑圧者側で、個人を標榜することは、たいていの場合、被抑圧者内部のエリートであり、またそう見られがちである。第三者の立場に至っては、せいぜい高みの見物か、日和見と見られる。 そのなかで、塩川氏は、労多くしても報われることの少ない作業を、接近・友好の姿勢を見せつつ行っていかなければならない、と説く。 評者が思うに、いわゆるマイノリティの運動が陥る陥穽として、マイノリティ集団が内部のさらなるマイノリティ集団や個人を抑圧することは、必然かどうかはともかくとして、日常的に見られることである。これに対し個人は、極めて強大なエリートでない限り、これに抗することは困難である。
しかし、一方でマイノリティ集団内部での多極化も、ここ十数年の間に急速に進んでいるのではないか。すなわち、個々の個人が個人としての立場を、自らの意思で選択するか否かを問わず、集団内部が急速に流動化しているのである。このことは、確かにマジョリティ集団に対する対抗力を弱めることになる。しかし、流動化した個人の動きが、思わぬ方向で抑圧者/被抑圧者の垣根を崩す可能性を秘めている、というよりそのような流動かは既に現実である。評者は、自己決定権というようなことが言われ始めた背景には、このような事情があると考えているが、如何だろうか。 岩瀬民可子氏の「『女性の権利擁護』を読み直す」、瀬知山角氏の「性の商品化とリベラリズム」については、簡単に触れるに止めるが、両者ともフェミニズムとリベラリズムの距離についての、意欲的な論考である。 岩瀬氏は、18世紀のフェミニストである、メアリ・ウルストンクラフトの表記著作を再読する。この中で、フェミニズムは当初より、リベラリズムとは質的な差異を持つものとして捉えられていたことを指摘する。そして、その差異とは、「徳」(virtue)であるという。すなわち、「女性」であることの定義づけを自らの手によって行うこと、それを基に、女性として公共善に対し貢献することであったという。公共善の内容(とりわけ現代的意義での)には疑問も残るが、公共的空間への参加の手続的保障には関心を覚える。
瀬知山氏は、セックスワークとリベラリズム、の問題につき、この国における歴史的、文化的経緯を検証しつつ、性に関する自己決定が成立する条件を模索する。すなわち、保守主義からと、近代主義からの双方の性の商品化批判を退け、特定の規範が支配することを拒否する。その上で、当事者の一方にのみ責任を課すことなく、当事者双方が自己決定するための、情報提供と教育の必要性を説く。その具体的方策はここで示されているわけではないが、理念にとどまらず論争を丁寧に解きほぐす姿勢は大変評価すべきものである。 この点、永田えり子氏の「『性的自己決定権』批判」は、読む者を困惑へと誘う。永田氏は、例えば宮台真司氏らの「性の自己決定」言説につき、リベラリズムと異なるリバータリアニズムと規定し、それが性別に関する平等や個人の解放につながらない、という。 確かに、いわゆる自己決定権を唱える者の一部には、永田氏の言うような「最小国家論」を含むようなリバータリアニズム(一般的には、「新保守主義」と言われる)に立脚する者もいる。そして、この立場に関しては、永田氏の危惧するような、(男性優位の)暗黙の価値前提やそれに伴う不公正の温存、さらには強者優遇といった批判は妥当する。 しかし、自己決定権に関する議論は、上記リバータリアニズムに固有のものではない。すなわち、一定の国家的介入を是認するリベラリズムからも導き出される。永田氏が意図したものかどうかは知らないが、自己決定論の問題点とリバータリアニズムの問題点は、致命的までに混同されている。 さらに、氏は「自己決定」言説の矛盾らしきものの指摘を行...