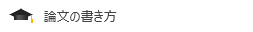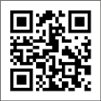資料紹介
J.ラウズ著(成定・網谷・阿曽沼共訳)『知識と権力--クーン/ハイデガー/フーコー』
法政大学出版局, 2000年, pp.369 + 39.
訳者あとがき
本書『知識と権力--クーン/ハイデガー/フーコー』は、Rouse, J., Knowledge and Power: Toward a Political Philosophy of Science, Cornell U.P., 1987の全訳である。原題のうち、副題の部分は、直訳すれば「科学の政治哲学へ向けて」ということになるだろう。しかし、邦訳の副題としては、本書の叙述と展開の中で重要な役割を演じている三人の思想家、クーン、ハイデガー、フーコーを列挙することによって、著者ラウズの科学論の方向性を示唆することとした。
言うまでもなく、クーン、ハイデガー、フーコーの三人は、二十世紀の学問と思想の世界に巨大な影響力を及ぼした思想家である。次の世紀も、少なくとも当分の間、彼らの影響力が衰えることはあるまい。とはいえ一般には、この三人の思想と学問は、互いに異質あるいは無関係と思われているのではあるまいか。したがって、邦訳の副題として、三人の名前を並記することに若干のためらいがなかったわけではない。しかし、ラウズは本書において、これら三人が提起した概念や方法を大胆に拡張し、さらにそれらを融合することによって、自らの科学論を構築している。
すなわち、クーンからは「実践としての科学」という概念を、ハイデガーからは「実践的解釈学」の方法を、フーコーからは「知識と権力」の関係をめぐる新しい見方をそれぞれ取り入れることによって、ラウズは実験室の中で科学知識が作り出されていくプロセスを活写し分析している。そのような分析を通じて、ラウズは、自然に関する認識(自然科学)と人間・社会に関する認識(人間科学)の間には、方法においても、また知識の本性においても、本質的な差異はないと論じ(だからといって、両者が全く同じだと主張しているわけでもない)、さらに、科学知識生成の場としての実験室は、フーコーのいう「規律・訓練の施設」の一つに他ならない、といった大胆な主張を提示しているのである。
ヨーロッパの哲学思想と英米圏の科学哲学の架橋というラウズのモチーフについて、また、自然認識にも解釈という行為が不可避であること、その意味では自然科学と人間科学の間に本質的な差異はないというラウズの主張について、類似した試みとして、われわれにはすでに野家啓一氏の先駆的で野心的な論考がある(『科学の解釈学』新曜社、一九九三年)。道具立てと論述の筋道に違いはあっても、大筋で両者(ラウズと野家氏)が同じ方向を指さしていることは間違いないし、科学論の最も重要で肥沃な論点がここにあることもまた衆目の一致するところであろう。(もっとも、野家氏自身は、「科学の解釈学」から「科学のナラトロジー」へと問題関心を移しつつあるとのことだし、後述するように、ラウズは近年、「科学のカルチュラル・スタディーズ」に着目しているようである。)
フーコーを科学論の中に位置づけるという試みについて言えば、以前、訳者らが邦訳したG・ガッティング『理性の考古学--フーコーと科学思想史』(産業図書、一九九二年)に先駆的な事例がある。しかし、ガッティングの論述と分析は『知の考古学』にとどまっており、『監獄の誕生』と『性の歴史』には及んでいなかった。桜井哲夫氏の卓抜なフーコー論(『フーコー--知と権力』講談社、一九九八年)からもみてとれるように、フーコー思想の真骨頂が晩年の
タグ
 All rights reserved.
All rights reserved.
資料の原本内容
J.ラウズ著(成定・網谷・阿曽沼共訳)『知識と権力--クーン/ハイデガー/フーコー』
法政大学出版局, 2000年, pp.369 + 39.
訳者あとがき
本書『知識と権力--クーン/ハイデガー/フーコー』は、Rouse, J., Knowledge and Power: Toward a Political Philosophy of Science, Cornell U.P., 1987の全訳である。原題のうち、副題の部分は、直訳すれば「科学の政治哲学へ向けて」ということになるだろう。しかし、邦訳の副題としては、本書の叙述と展開の中で重要な役割を演じている三人の思想家、クーン、ハイデガー、フーコーを列挙することによって、著者ラウズの科学論の方向性を示唆することとした。
言うまでもなく、クーン、ハイデガー、フーコーの三人は、二十世紀の学問と思想の世界に巨大な影響力を及ぼした思想家である。次の世紀も、少なくとも当分の間、彼らの影響力が衰えることはあるまい。とはいえ一般には、この三人の思想と学問は、互いに異質あるいは無関係と思われているのではあるまいか。したがって、邦訳の副題として、三人の名前を並記することに若干のためらいがなかったわけではない。しかし、ラウズは本書において、これら三人が提起した概念や方法を大胆に拡張し、さらにそれらを融合することによって、自らの科学論を構築している。
すなわち、クーンからは「実践としての科学」という概念を、ハイデガーからは「実践的解釈学」の方法を、フーコーからは「知識と権力」の関係をめぐる新しい見方をそれぞれ取り入れることによって、ラウズは実験室の中で科学知識が作り出されていくプロセスを活写し分析している。そのような分析を通じて、ラウズは、自然に関する認識(自然科学)と人間・社会に関する認識(人間科学)の間には、方法においても、また知識の本性においても、本質的な差異はないと論じ(だからといって、両者が全く同じだと主張しているわけでもない)、さらに、科学知識生成の場としての実験室は、フーコーのいう「規律・訓練の施設」の一つに他ならない、といった大胆な主張を提示しているのである。
ヨーロッパの哲学思想と英米圏の科学哲学の架橋というラウズのモチーフについて、また、自然認識にも解釈という行為が不可避であること、その意味では自然科学と人間科学の間に本質的な差異はないというラウズの主張について、類似した試みとして、われわれにはすでに野家啓一氏の先駆的で野心的な論考がある(『科学の解釈学』新曜社、一九九三年)。道具立てと論述の筋道に違いはあっても、大筋で両者(ラウズと野家氏)が同じ方向を指さしていることは間違いないし、科学論の最も重要で肥沃な論点がここにあることもまた衆目の一致するところであろう。(もっとも、野家氏自身は、「科学の解釈学」から「科学のナラトロジー」へと問題関心を移しつつあるとのことだし、後述するように、ラウズは近年、「科学のカルチュラル・スタディーズ」に着目しているようである。)
フーコーを科学論の中に位置づけるという試みについて言えば、以前、訳者らが邦訳したG・ガッティング『理性の考古学--フーコーと科学思想史』(産業図書、一九九二年)に先駆的な事例がある。しかし、ガッティングの論述と分析は『知の考古学』にとどまっており、『監獄の誕生』と『性の歴史』には及んでいなかった。桜井哲夫氏の卓抜なフーコー論(『フーコー--知と権力』講談社、一九九八年)からもみてとれるように、フーコー思想の真骨頂が晩年の二つの著作(『監獄の誕生』と『性の歴史』)にあるとすれば、この二つの著作を科学論の文脈に読み込んでみせた、本書におけるラウズの大胆な試みは、ガッティングの論述の欠を補うだけでなく、科学論とフーコー論の双方に新しい問題領域を切り拓いたといえよう。
本書は、いわゆる「サイエンス・ウォーズ」の文脈で読まれることが予想される。サイエンス・ウォーズとは、「相対主義的科学論」あるいは「ポストモダン科学論」に対する科学者たちの反発ないし批判に端を発する論争であるが、本書で展開されているラウズの科学論を、サイエンス・ウォーズで論難されている「ポストモダン科学論」の亜種と断じて批判する向きがあるかもしれないからである。(サイエンス・ウォーズについては、『現代思想』一九九八年十一月号、および金森修『サイエンス・ウォーズ』東京大学出版会、二○○○年などを参照。)
折しも、サイエンス・ウォーズの火付け役であるA・ソーカルらの著作が翻訳出版されたばかりだし(田崎・大野・堀訳『「知」の欺瞞--ポストモダン思想における科学の濫用』岩波書店、二○○○年)、ポストモダン科学論の主要な論客であるB・ラトゥールの主著もすでに翻訳出版されているので(川崎・高田共訳『科学が作られているとき--人類学的考察』産業図書、一九九九年)、本書が「サイエンス・ウォーズ」の文脈で読まれることは致し方ないとしても、その文脈ないし図式でのみ読まれ論ぜられるのは、ラウズの本意ではあるまいし、訳者らにとっても残念なことである。
なぜならラウズは、科学に関してことさら奇矯な言辞を弄している--ソーカルらは、あたかもポストモダン科学論が、そうであるかのように戯画化して論難している--わけではないからである。むしろ、本書を一読すれば明らかなように、ラウズの科学論の根底ないし出発点には、科学の普遍的な応用可能性、また、科学が技術と結びついた場合の圧倒的な力に関する素朴で常識的な認識がある。科学に関するそのような素朴で常識的な認識を、自然と科学知識の「本性」に安易に還元することなく説明してみせること、すなわち、「科学の成功は、科学知識が自然を忠実に反映しているからであり、それ故、科学知識は普遍的に応用可能である(科学は成功しているから正しい、正しいから成功する)」といった循環論法に陥らずに説明してみせること、にラウズ科学論の課題と目標がある。それがどの程度成功しているかについて、読者の判断と批判をまちたいと訳者らは願っている。
訳者らが本書に出会ったのは、ずいぶん前のことであった。もはや何年前かの記憶も定かではないが、訳者の一人(阿曽沼)が、別の訳者(成定)のもとを訪れて、「科学と社会の関係について論じた面白い書物はないでしょうか」と質問したことがそもそものはじまりであった。さっそく、成定研究室の蔵書のうち、タイトルに「科学と社会」という語が含まれている研究書を取り出して、二人で何冊か検討してみたが、いまいちピンとこない。二人の問題意識と噛み合わなかったのである。試行錯誤をくり返して、ようやく本書とめぐりあった。ラウズの論述に、共鳴するものがあったのである。というのも、二人には、それぞれ理工系のキャリアがあり、実験室の空気を吸った経験があるのだが、そのような経験に照らしてみたとき、本書の第4章「ローカル・ノレッジ」における論述、すなわち、実験室とは何か、そこで何が行われているかをめぐるラウズの論述は、きわめてリアルで納得のいくものだったのである。「これは面白い」ということになった。以前、クーンの『科学革命の構造』に出会った時のショックというか興奮を思い起こしたものであった。
読書会形式で本書を少しずつ読み進めていたが、そのうち、阿曽沼が東京で仕事をすることになり、読書会は中断を余儀なくされた。しかし、せっかく面白い本に出会ったのだから、自分たちの手で日本語にしてみたいと考えて、原著出版社に邦訳出版の可能性について打診したところ、すぐ承諾の返事がきた。第1章と第2章について、阿曽沼が下訳し、成定が手を入れるという段取りで、邦訳作業にも着手した。
とはいえ、本書のような商業的成功の見込みの少ない書物の邦訳出版をどこに依頼しようかと考えあぐねた。結局、これまでも何度か邦訳出版についてお世話になっている法政大学出版局の平川俊彦氏に照会したところ、あっさりと引き受けて下さることになった。一九九六年の春のことであった。それ以来、本格的に邦訳作業に取りかかった。ところが、東京で研究生活を送っていた阿曽沼は、いくつもの研究プロジェクトに関与し、さらには学位論文の執筆に忙殺されて、翻訳に多くの時間と労力を割くことが困難になった。やむなく、第3章以降についてはもっぱら成定が訳出することになったが、哲学プロパーの論議が大部分を占める第3、5、6章の訳出には難渋していた。そこで、当時、成定の近くで哲学を学んでいた網谷に、この三つの章について訳文・訳語のチェックを依頼したところ、朱筆で真っ赤になった訂正原稿が戻ってきた。爾来、網谷も訳者に加わわることになった。以上のような経緯で、阿曽沼は第1、2章(と第4章の一部)の下訳について、網谷は第3、5、6章の改善について、それぞれ寄与したが、(本書の基本概念を借りれば)訳者三人の間の「(当面の)権力関係」からして、本訳書全体の責任は成定にある。
訳者らは、先に機会を得て、ラウズの近著Engaging Science, How to Understand Its Practices Philosophically, Cornell U.P., 1996から、その第9章"What are the Cultural Studies of Science"を訳出紹介した(成定・阿曽沼訳「科学のカルチュラル・スタディーズとは何か」、『現代思想』一九九六年五月号、三○八-三二四頁)。原著の発行年からすると順序が逆になってしまったが、本訳書の...