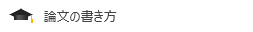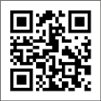資料紹介
科学とは何か--「二つの文化」論から「知のモード」論へ
科学の独立と科学者の誕生
英語のscientist(科学者)という言葉が創られたのは1830年代のことであった。すでにscienceという言葉はあったが、philosophyとほぼ同義語として用いられており、ともに広い意味での知的探求(哲学)とその成果としての知識を意味していた。したがって、自然を対象とした知的探求は哲学の一部としての自然哲学(natural philosophy)であり、例えば、ニュートン(1642-1727)は、自然哲学者(natural philosopher)と呼ばれたのである。しかし、19世紀になると、philosophy(哲学)から、自然を対象とし実験や観察を方法とする固有の学問分野としてのscience(科学)が独立し、科学を探究する専門家としての科学者が誕生したのである。
「科学の独立」と「科学者の誕生」は、教育・研究の場としての大学の発展拡大と時期を同じくしていた。中世以来の伝統を有するヨーロッパの大学では、(自然)科学を教え研究する部門はなかったのだが、19世紀を通じて自然科学の教育・研究が次第に拡充強化され、科学者が養成されるようになった。従来の人文的伝統を中心とした大学・知識社会の中に、新しく科学的伝統が加わったったのである。科学は次々に新しい専門分野を開拓して勢力を拡大するとともに、20世紀に入ると技術と深く結びつき、「科学技術」として経済社会や政治に大きな影響を及ぼすに至った。
スノーの「二つの文化」論とクーンの科学論
科学の専門細分化と科学技術の影響力の拡大の結果、深刻な文化的危機が生じつつあるのではないかとの懸念が表明された。1959年、イギリスの著作家C.P.スノー(1905-1980)は「二つの文化と科学革命」と題された講演で、科学革命(20世紀前半における科学技術の発展をスノーは「科学革命」と呼んだ)の結果、西欧の知識人社会に大きな亀裂が生じつつあると論じたのである。すなわち、スノーは人文的文化(その代表としての文学者)と科学的文化(その代表としての物理学者)の間には越えがたい亀裂=溝があり、両者は互いに理解しあうことができず、言葉さえ通じなくなってしまっていると論じ、これは西欧文化における危機だと警鐘を鳴らしたのである。スノー自身、物理学者としての経験をもつ評論家・小説家という特異なキャリアの持ち主であり、文化の分裂に深刻な懸念を抱いたのであった。文化の分裂という危機に対するスノーの処方箋は、科学革命という現実を踏まえて、文系知識人が科学技術に対する基本的な認識と理解をもつよう努力すべきではないか、というものであった。
スノーの講演の数年後、クーンの『科学革命の構造』が出版された(1962年)。物理学者から科学史家に転じたT.S.クーン(1922-1996)は、科学研究は「一般に認められた科学的業績で、一時期の間、専門家に対して問い方や答え方のモデルを与える」パラダイム(paradigm)を基盤に遂行されると論じ、科学の歴史を「パラダイム・チェンジ=科学革命」の歴史と捉えた。クーンの科学論は従来の累積的・連続的な科学史観を根底からくつがえすとともに、自然科学(の各専門分野)には明確なパラダイムがあるが、人文・社会科学にはパラダイムがみてとれないと論じて、自然科学と人文・社会科学の差異を浮き彫りにし、「二つの文化」の存在を科学論の立場から裏付けた。
総合科学の試み
このように、1960年代には、事態を憂慮するかどうかは
タグ
 All rights reserved.
All rights reserved.
資料の原本内容
科学とは何か--「二つの文化」論から「知のモード」論へ
科学の独立と科学者の誕生
英語のscientist(科学者)という言葉が創られたのは1830年代のことであった。すでにscienceという言葉はあったが、philosophyとほぼ同義語として用いられており、ともに広い意味での知的探求(哲学)とその成果としての知識を意味していた。したがって、自然を対象とした知的探求は哲学の一部としての自然哲学(natural philosophy)であり、例えば、ニュートン(1642-1727)は、自然哲学者(natural philosopher)と呼ばれたのである。しかし、19世紀になると、philosophy(哲学)から、自然を対象とし実験や観察を方法とする固有の学問分野としてのscience(科学)が独立し、科学を探究する専門家としての科学者が誕生したのである。
「科学の独立」と「科学者の誕生」は、教育・研究の場としての大学の発展拡大と時期を同じくしていた。中世以来の伝統を有するヨーロッパの大学では、(自然)科学を教え研究する部門はなかったのだが、19世紀を通じて自然科学の教育・研究が次第に拡充強化され、科学者が養成されるようになった。従来の人文的伝統を中心とした大学・知識社会の中に、新しく科学的伝統が加わったったのである。科学は次々に新しい専門分野を開拓して勢力を拡大するとともに、20世紀に入ると技術と深く結びつき、「科学技術」として経済社会や政治に大きな影響を及ぼすに至った。
スノーの「二つの文化」論とクーンの科学論
科学の専門細分化と科学技術の影響力の拡大の結果、深刻な文化的危機が生じつつあるのではないかとの懸念が表明された。1959年、イギリスの著作家C.P.スノー(1905-1980)は「二つの文化と科学革命」と題された講演で、科学革命(20世紀前半における科学技術の発展をスノーは「科学革命」と呼んだ)の結果、西欧の知識人社会に大きな亀裂が生じつつあると論じたのである。すなわち、スノーは人文的文化(その代表としての文学者)と科学的文化(その代表としての物理学者)の間には越えがたい亀裂=溝があり、両者は互いに理解しあうことができず、言葉さえ通じなくなってしまっていると論じ、これは西欧文化における危機だと警鐘を鳴らしたのである。スノー自身、物理学者としての経験をもつ評論家・小説家という特異なキャリアの持ち主であり、文化の分裂に深刻な懸念を抱いたのであった。文化の分裂という危機に対するスノーの処方箋は、科学革命という現実を踏まえて、文系知識人が科学技術に対する基本的な認識と理解をもつよう努力すべきではないか、というものであった。
スノーの講演の数年後、クーンの『科学革命の構造』が出版された(1962年)。物理学者から科学史家に転じたT.S.クーン(1922-1996)は、科学研究は「一般に認められた科学的業績で、一時期の間、専門家に対して問い方や答え方のモデルを与える」パラダイム(paradigm)を基盤に遂行されると論じ、科学の歴史を「パラダイム・チェンジ=科学革命」の歴史と捉えた。クーンの科学論は従来の累積的・連続的な科学史観を根底からくつがえすとともに、自然科学(の各専門分野)には明確なパラダイムがあるが、人文・社会科学にはパラダイムがみてとれないと論じて、自然科学と人文・社会科学の差異を浮き彫りにし、「二つの文化」の存在を科学論の立場から裏付けた。
総合科学の試み
このように、1960年代には、事態を憂慮するかどうかは別にして、知識社会は大きく二つ(文系と理系)に分断されているとの認識が共有された。実際、、学問の高度化に伴って、文系と理系それぞれの内部で際限のない専門細分化が進行した。その動きは、現在も継続しているとみることもできる。知識社会には「二つの文化」どころか「百の文化」が存在する状況となったのである。
しかし、その一方で1970年代以降、専門細分化した学問では対応できないような問題がクローズアップされるようになった。代表的な問題が公害・環境問題であり、エネルギー問題である。あるいは脳死・移植医療など先端医療をめぐる諸問題である。細分化された個別学問ではこれらの問題に対処することはできない。理系・文系にまたがる学際科学ないしは総合科学が求められるにいたった所以である。このような動きの中で、広島大学では1974年に総合科学部が設置された。総合科学部は、総合科学の研究と教育の確立に尽力してきたが、創設当初から現在にいたるまで、「総合科学とは何か」をめぐる議論は継続している。専門分野の壁(「百の文化」の壁)が高く、総合科学の実践は容易ではないからである。
「知のモード」論とコンピュータ革命
専門家が自らの専門分野にこだわり続ける限り総合科学の実践は困難だが、情報化社会の進展(コンピュータ革命とインターネットの登場)が、突破口を切りひらいてくれるかもしれない。ギボンズらは、専門分野に依拠した伝統的な知識生産をモード1と呼び、専門分野を越えた知識生産をモード2と呼ぶ。モード1の知識生産はもっぱら大学で行われてきたし、現在も継続して行われている。一方、情報化社会の進展によって、大学以外のさまざまな場所(企業、官庁、NGO、NPOなど)における知識の生産と加工が容易となり、専門分野を越えたモード2の知識生産が可能となった、というのである。例えば、ある問題を解決するために、インターネットを駆使して多くの情報を収集するとともに、その過程で多くの専門家から成る人的ネットワークを構築していくというモード2的な知識生産は、総合科学の実践に他ならないだろう。
スノーは科学革命が文化に亀裂を生じさせたと憂慮したが、コンピュータ革命は、知識社会に生じた亀裂を乗り越えて、総合科学の実践を容易にしてくれる可能性をもっているのである。そのような実践が数多く積み重ねられることによって、二つどころか百にも二百にも分裂した文化が再び一つに統合されることも夢ではあるまい。少なくとも、教育や研究に携わるものは、その方向で努力すべきではないだろうか。
参考文献
C.P.スノー(松井巻之助訳)『二つの文化と科学革命』みすず書房、1967年。
マイケル・ギボンズ(小林信一監訳)『現代社会と知の創造ムモード論とは何か』丸善ライブラリー、1997年。
T.クーン(中山茂訳)『科学革命の構造』みすず書房、1971年。
資料提供先→ http://home.hiroshima-u.ac.jp/nkaoru/Fukuyamalecture.html