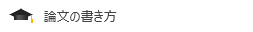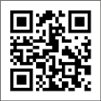資料紹介
D・オースター『ネイチャーズ・エコノミー--エコロジー思想史』リブロポート、一九八九年、四八二 + X 頁。
訳者あとがき
本書の訳業に本格的に着手してから約六年になる。本書訳出のきっかけは、共訳者の一人である中山茂氏の論考「環境史の可能性」(『歴史と社会』創刊号、一九八二年)であった。この論考の発表を契機にして邦訳出版の話が具体化し、訳出には、中山氏の他、吉田忠氏と成定があたった。諸般の事情から、最終的な訳業の分担は、「はしがき」、「新版への序」、第一章、第二章の前半(五~五一頁)は中山氏、第十章、第十一章(二三五~二七一頁)は吉田氏、それ以外はすべて成定となった。なお、第二部訳出にあたっては、牛山輝代氏(国立音楽大学)が作られた訳稿を活用させていただいた。全体の八割以上を成定が担当したこと、最終段階で中山氏が長期の海外出張に出たりしたことなどから、訳文・訳語の整理も含めて訳業全体のとりまとめには成定があたった。
今、訳語の整理と書いたが、この面倒な作業は翻訳にはつきものとはいえ、本書についてはこれが最初から最後まで頭痛の種であった。まず、書名ともなっているnature's economyあるいはeconomy of nature をどう訳すか? この言葉は、当然にも本書全体のキーワードなのだからあだや疎かにはできない。結局、邦訳書のタイトルとしては、カタカナ表記のままに残し、本文では「自然の経済」と訳した上で、要所要所でカタカナを添えた。また、もっとも苦労したのはnatural history という語であり、それとの関連でnatural historian およびnaturalistをどう訳すかであった。natural history には、伝統的に「博物学」という訳語があてられているが、博物学という語は古めかしいというか、黴臭いニュアンスがつきまとっている。これを避けるために、近年は「自然誌」ないし「自然史」という訳語があてられる場合が多い。他にも「博物誌」「博物史」などという語も考えられるし、じっさい用いられてもいる。natural historian およびnaturalistについては、それぞれの語に「者」ないし「家」をつけることになる・・博物学者、自然誌家といった具合である。訳業を進めていく過程で、どの語を採用すべきかをめぐって、訳者の間でしばしば論議を重ねたのだが、一向に名案が浮かばない。どの訳語にも微妙なニュアンスがあって、本訳書全体を一つの流儀で統一するのは無理があるように思えたからである。かといって何もかもカタカナで済ますというのは余りにも芸がない。そんな風に訳業が滞っているうちに、例えば荒俣宏氏の精力的な仕事を通じて、古めかしかったはずの博物学という語が新たな息吹を与えられ、一部では博物学ルネッサンスといった状況も見られるようになってきた。まことに言葉は生き物である。結局、一つのやり方で統一することは断念して、各部・各章の文脈でもっともふさわしいと思われる語をあて、要所要所でカタカナを添えることにした。その結果、例えば、第一部の主要な登場人物G・ホワイトには概ね「自然研究家」という語を、また第二部の主人公H・D・ソローにはもっぱら「ナチュラリスト」という表現をあてることにした。
同じ事情はecology,ecologist についてもいえる。ecology,ecologist を機械的に「生態学」「生態学者」とすると、落ち着きのよくないところが多々ある。「エコロジー」なり「エコロジスト」としたほうがぴったりくる
 All rights reserved.
All rights reserved.
資料の原本内容
D・オースター『ネイチャーズ・エコノミー--エコロジー思想史』リブロポート、一九八九年、四八二 + X 頁。
訳者あとがき
本書の訳業に本格的に着手してから約六年になる。本書訳出のきっかけは、共訳者の一人である中山茂氏の論考「環境史の可能性」(『歴史と社会』創刊号、一九八二年)であった。この論考の発表を契機にして邦訳出版の話が具体化し、訳出には、中山氏の他、吉田忠氏と成定があたった。諸般の事情から、最終的な訳業の分担は、「はしがき」、「新版への序」、第一章、第二章の前半(五~五一頁)は中山氏、第十章、第十一章(二三五~二七一頁)は吉田氏、それ以外はすべて成定となった。なお、第二部訳出にあたっては、牛山輝代氏(国立音楽大学)が作られた訳稿を活用させていただいた。全体の八割以上を成定が担当したこと、最終段階で中山氏が長期の海外出張に出たりしたことなどから、訳文・訳語の整理も含めて訳業全体のとりまとめには成定があたった。
今、訳語の整理と書いたが、この面倒な作業は翻訳にはつきものとはいえ、本書についてはこれが最初から最後まで頭痛の種であった。まず、書名ともなっているnature's economyあるいはeconomy of nature をどう訳すか? この言葉は、当然にも本書全体のキーワードなのだからあだや疎かにはできない。結局、邦訳書のタイトルとしては、カタカナ表記のままに残し、本文では「自然の経済」と訳した上で、要所要所でカタカナを添えた。また、もっとも苦労したのはnatural history という語であり、それとの関連でnatural historian およびnaturalistをどう訳すかであった。natural history には、伝統的に「博物学」という訳語があてられているが、博物学という語は古めかしいというか、黴臭いニュアンスがつきまとっている。これを避けるために、近年は「自然誌」ないし「自然史」という訳語があてられる場合が多い。他にも「博物誌」「博物史」などという語も考えられるし、じっさい用いられてもいる。natural historian およびnaturalistについては、それぞれの語に「者」ないし「家」をつけることになる・・博物学者、自然誌家といった具合である。訳業を進めていく過程で、どの語を採用すべきかをめぐって、訳者の間でしばしば論議を重ねたのだが、一向に名案が浮かばない。どの訳語にも微妙なニュアンスがあって、本訳書全体を一つの流儀で統一するのは無理があるように思えたからである。かといって何もかもカタカナで済ますというのは余りにも芸がない。そんな風に訳業が滞っているうちに、例えば荒俣宏氏の精力的な仕事を通じて、古めかしかったはずの博物学という語が新たな息吹を与えられ、一部では博物学ルネッサンスといった状況も見られるようになってきた。まことに言葉は生き物である。結局、一つのやり方で統一することは断念して、各部・各章の文脈でもっともふさわしいと思われる語をあて、要所要所でカタカナを添えることにした。その結果、例えば、第一部の主要な登場人物G・ホワイトには概ね「自然研究家」という語を、また第二部の主人公H・D・ソローにはもっぱら「ナチュラリスト」という表現をあてることにした。
同じ事情はecology,ecologist についてもいえる。ecology,ecologist を機械的に「生態学」「生態学者」とすると、落ち着きのよくないところが多々ある。「エコロジー」なり「エコロジスト」としたほうがぴったりくる場合があるのである。共訳者の一人である吉田氏はいみじくも「生態学とエコロジー」と題した論考を発表している(『歴史と社会』第4号、一九八四年)。結局、学問的・アカデミックな文脈では「生態学」「生態学者」を、思想的・運動的な文脈では「エコロジー」「エコロジスト」を用いることにしたが、もちろん、どちらとも判断のつかない場合もあり、最後まで神経を擦り減らした。一つの語で複雑な含意を表現できる英語は日本語よりも表現力に富んでいるのだろうか、それとも、一つの英単語に多くの訳語をあてることができる(あてねばならない)のは、日本語の豊かな造語力の証拠なのだろうか? おそらく、単にどちらの言語が表現力に富んでいるかといったことに論点があるのではなく、翻訳をめぐるこの困難さは、明治以来我が国の学術・思想が欧米のそれらに学んできたという周知の事実が深く絡んでいるのだろう。ともあれ、このような事情を忖度しながら本訳書を読んでいただければ、natural history やecology のたどった歴史的変遷--そこから複雑な含意も生まれてきたわけだが--について読者は一層理解を深めていただけるだろう。そもそも、著者オースターの本書における主題は、自然観や環境観にまつわる言葉や概念の歴史を跡づけるということにほかならなかったのである。
中山氏や吉田氏が『歴史と社会』誌で、主としてアメリカの学界・思想界の動向を踏まえて、環境史や生態学史の重要性を訴えた一九八○年代前半、我が国では環境問題についての関心はすっかり下火になっていた。ジャーナリズムでも学界でも公害・環境問題を論ずることは流行遅れの感が強かった。七○年代の公害・環境問題にたいする関心の高まりの中で各地の大学に設置された環境科学系のコース・学科は、八○年代前半、社会的なサポートの衰退とともに、ややもすれば方向を見失いがちであった。じつは、成定が本訳業に取り組むことになったのは、当時、勤務先の大学で「環境科学コース」を担当していたという「職務上のex officio義務感」に由来していたのである。しかし、訳業を進めている間に、成定が関与していた「環境科学研究科(大学院)」も「環境科学コース(学部)」もそれぞれ大学院と学部の組織替えに伴って「発展的に」解消してしまった。その結果、成定は大学院担当を免ぜられることになり、おかげで「職務上の義務感」からは大幅に解放されることになったのだが、このような事態の推移に、八○年代前半の「環境」をめぐる状況が象徴されているように思われる。
ところが、八○年代も終わろうする頃、突然、「環境」への関心が復活した。昨年(一九八八年)から今年にかけて、マスコミ、ジャーナリズムでは地球温暖化、酸性雨、フロンガスによるオゾン層の破壊、熱帯雨林の破壊、砂漠化といった環境問題が日夜報道され、熱っぽく論議されている。このような風潮はそれ自体歓迎すべきこととはいえ、「環境フィーヴァー」の再来そのものついては、その政治的・思想的背景の分析が必要かとも思われる。それはともかく、このような状況の中で、環境思想・エコロジー思想の歴史を克明にたどった本訳書を送り出すのは、タイミングが良すぎていささか面映ゆい。じっさい、このところ我が国の出版界では生態学史や環境思想史関係の本格的な研究書の出版が相次いでいる。本書の原著(一九七七年刊行)以降出版された関連書のうち最近邦訳されたものを挙げれば、K・トマス(山内 監訳)『人間と自然界--近代イギリスにおける自然観の変遷』(法政大学出版局、一九八九年)、ロバート・P・マッキントッシュ(大串隆之・井上弘・曽田貞滋共訳)『生態学--概念と理論の歴史』(思索社、一九八九年)などがある。特に後者は、生態学の学説史(インターナル・ヒストリイ)として書かれたものであり、生態学の思想史(エクスターナル・ヒストリイ)としての本書と相補的な関係にある。
それにしても翻訳に要した六年という歳月は長かった。この間、訳者(成定)の身辺でも、公私ともどもいろいろなことが起こった。例えば、結婚と長女の誕生に加えて都心から郊外へという生活環境の変化を経験した。郊外の住宅地というのは、それ自体としては、自然環境の大規模破壊の産物以外のなにものでもないのだが、それでも、都心から移り住んだものにとっては、それなりに「豊かな自然」を提供してくれるのである--本書の言い方に従えば、自然に対する帝国主義的介入(宅地開発)を踏み台にして牧歌主義的な自然観を謳歌していることになるわけである。そのような出来事や経験を通じて、また本書の訳業それ自体を通じて、訳者は、人間や自然についてまた両者の相互関係について六年前よりは少しは理解を深めることができたように思うし、そう信じたい。また、前述したように、「職務上の義務感」からの解放という事情もあって、途中からは本書の固有の価値に促されて訳業にあたることができたのは幸いだった。しかし、生態学のみならず、政治・社会思想から文学や哲学におよぶ広範な内容を取り扱った本書の訳業は困難で、暗礁に乗り上げたこともしばしばであった。そのような時、身近に環境問題に強い関心と高い見識を有する同僚諸氏がいて、何かと相談に乗っていただけたのはありがたかった。また、久保山亮、鎌田磨人の両氏は訳者のもとめに応えて訳文・訳語を丹念にチェックして下さった。おかげで多くの誤りを正し、曖昧な部分をはっきりさせることができた。ここに記して謝意を表する次第である。とはいえ、六年の歳月の中で、訳者の自然観・人間観も変化し、また本書にたいするスタンスも変化したのだから、統一・整理に努めたものの、訳文の文体などにその変化が影を落としているかもしれない。誤解・誤読の箇所もあるだろう。読者諸賢の忌憚のない御批判・御教示を乞いたい。(一九八九年初秋)(中山茂氏、吉田忠氏と共訳)
追記--訳者ら(吉田忠と成定薫)は、昭和61・62年度科学研究補助金(総合研究A)による研究「自然...