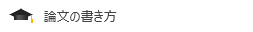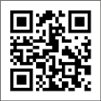資料紹介
エンタルピー
エントロピーとは別物だよ。
比熱
物体の温度を1℃上げるのに必要な熱量を「熱容量」という。 大きな物体ほど全体を温めるのに多くの熱が必要だから、その分だけ熱容量が大きいと言える。 熱容量が大きいほど温まりにくい。 温度を上げないで多くの熱を貯め込めるわけだ。
しかし物体の大きさによって熱容量が違うのでは物質の種類による比較が難しい。 それで、ある一定量あたりの熱容量というものを導入する。 これを「比熱容量」、略して「比熱」と呼ぶ。
用途によって、一定体積で比較する「容積比熱」、一定重量で比較する「重量比熱」などを使うこともあるが、熱化学では1mol あたりの熱容量を表す「モル比熱」をよく使う。 後で化学変化についても扱う予定なので、私の説明ではこれを採用しておくのがいいだろう。
まぁ、比熱も熱容量も量的な違いだけであって、本質的な意味では大きな差はないということだ。
熱容量を数式で表すと、温度が1℃変化する時の熱量の変化量という意味であるから次のようになる。
一方、モル比熱は、
と表すことになる。 教科書によっては 1/n を付けないで、熱容量も比熱も区別していないことがあるが、そういう本では理想気体の状態方程式として pV = RT を使っており、初めから1モルの気体の話だとして議論しているのだから問題はない。 (たまにその辺りがごちゃごちゃになっていてごまかしているものもある。)
私の説明では以前、理想気体の方程式として pV = nRT を使ってしまった。 つまり私が使っている体積 V は気体が n モルある時の体積を表しているのだから、そのことで問題が起こらないように面倒臭がらずにちゃんと区別しておこう。
熱力学の第1法則、
を変形すれば、
となる。 ここで突然だが、内部エネルギー U は T と V の関数になっていると考えよう。 ここまで内部エネルギー U やエントロピー S のように幾つかの新しい状態量を導入してきたが、結局は熱力学的な状態には変数2つ分の自由度しかないのであって、2つの変数さえあれば状態は決まってしまうのである。 すると dU は次のように書ける。
これを先ほどの式に代入すれば、
となる。 これを熱容量の定義式に代入すれば、
と表せることになるだろう。 このようにしたのは今後の計算に都合がいいからである。 U の独立変数として ( T, V ) ではなく、別の変数になっているとして計算しても構わないのだが、あまり使えない関係式が出来上がるだけである。 気になるなら後で試してみるのもいいだろう。
さてこの式を見れば、熱容量はいつも一定なのではなく、気体に課せられた条件によっても値が変わってくるだろうと想像が付く。
定積比熱
例えば、体積が変化しない容器内に密閉された気体の場合には dV = 0 なので
となる。 U の変数を T, V であるとしたのは、こういうすっきりした関係を導きたかったがためである。 他の組み合わせではこうは行くまい。 これを「定積熱容量」と呼ぶ。 n で割ってやれば「定積モル比熱」である。 この量は重要でよく使うので Cv と表すことが多い。
体積変化しないということは外部に対して仕事をしないわけで、与えられた全ての熱が温度上昇に使われるということだ。 つまり温度が上がりやすいことを意味し、熱容量は小さめになる。
定圧比熱
一方、大きなビニール袋に気体が少量だけ入れられたような状態を考える。 熱を加えられるとこの気体の体
タグ
 All rights reserved.
All rights reserved.
資料の原本内容
エンタルピー
エントロピーとは別物だよ。
比熱
物体の温度を1℃上げるのに必要な熱量を「熱容量」という。 大きな物体ほど全体を温めるのに多くの熱が必要だから、その分だけ熱容量が大きいと言える。 熱容量が大きいほど温まりにくい。 温度を上げないで多くの熱を貯め込めるわけだ。
しかし物体の大きさによって熱容量が違うのでは物質の種類による比較が難しい。 それで、ある一定量あたりの熱容量というものを導入する。 これを「比熱容量」、略して「比熱」と呼ぶ。
用途によって、一定体積で比較する「容積比熱」、一定重量で比較する「重量比熱」などを使うこともあるが、熱化学では1mol あたりの熱容量を表す「モル比熱」をよく使う。 後で化学変化についても扱う予定なので、私の説明ではこれを採用しておくのがいいだろう。
まぁ、比熱も熱容量も量的な違いだけであって、本質的な意味では大きな差はないということだ。
熱容量を数式で表すと、温度が1℃変化する時の熱量の変化量という意味であるから次のようになる。
一方、モル比熱は、
と表すことになる。 教科書によっては 1/n を付けないで、熱容量も比熱も区別していないことがあるが、そういう本では理想気体の状態方程式として pV = RT を使っており、初めから1モルの気体の話だとして議論しているのだから問題はない。 (たまにその辺りがごちゃごちゃになっていてごまかしているものもある。)
私の説明では以前、理想気体の方程式として pV = nRT を使ってしまった。 つまり私が使っている体積 V は気体が n モルある時の体積を表しているのだから、そのことで問題が起こらないように面倒臭がらずにちゃんと区別しておこう。
熱力学の第1法則、
を変形すれば、
となる。 ここで突然だが、内部エネルギー U は T と V の関数になっていると考えよう。 ここまで内部エネルギー U やエントロピー S のように幾つかの新しい状態量を導入してきたが、結局は熱力学的な状態には変数2つ分の自由度しかないのであって、2つの変数さえあれば状態は決まってしまうのである。 すると dU は次のように書ける。
これを先ほどの式に代入すれば、
となる。 これを熱容量の定義式に代入すれば、
と表せることになるだろう。 このようにしたのは今後の計算に都合がいいからである。 U の独立変数として ( T, V ) ではなく、別の変数になっているとして計算しても構わないのだが、あまり使えない関係式が出来上がるだけである。 気になるなら後で試してみるのもいいだろう。
さてこの式を見れば、熱容量はいつも一定なのではなく、気体に課せられた条件によっても値が変わってくるだろうと想像が付く。
定積比熱
例えば、体積が変化しない容器内に密閉された気体の場合には dV = 0 なので
となる。 U の変数を T, V であるとしたのは、こういうすっきりした関係を導きたかったがためである。 他の組み合わせではこうは行くまい。 これを「定積熱容量」と呼ぶ。 n で割ってやれば「定積モル比熱」である。 この量は重要でよく使うので Cv と表すことが多い。
体積変化しないということは外部に対して仕事をしないわけで、与えられた全ての熱が温度上昇に使われるということだ。 つまり温度が上がりやすいことを意味し、熱容量は小さめになる。
定圧比熱
一方、大きなビニール袋に気体が少量だけ入れられたような状態を考える。 熱を加えられるとこの気体の体積は増えるだろう。 その分だけ外部に仕事をすることになり、温度上昇の割合が小さくなる。 つまり定積の場合よりも熱容量が増したように感じられることになる。
爆発的に膨らむのでない限り、この体積変化は外部の気圧と釣り合う形で起こるわけで、このような状況での気体の熱容量を「定圧熱容量」と呼ぶ。 それを n で割ったものは「定圧モル比熱」であって、 Cp で表される。
この Cp の式は Cv に比べてどうにもややこしい。 以前に出てきた定圧膨張率 β を使ってみたがこれが精一杯である。 何とかならないものか後で考えてみよう。
その前に「定圧」に関連して、念のために幾つか説明しておこう。 もし袋の外が真空ならば袋は少量の気体を入れただけで一杯に膨らむことになる。 ただし内圧は低いので、もしこれに触れば不安定なシャボンのように振舞うだろう。 普段の我々の身の回りではそんな状態は見られないが、それは一定の気圧によって袋全体が外部から押されているために内部の気体の圧力と釣り合う所まで袋がしぼまされているのである。
気体の入ったビニール袋が大気中に置かれてさえいれば「定圧」になっているとは限らない。 気体が袋一杯に入っている場合は気体はむしろ袋の張力で押さえ込まれている状態になっている。 キンキンに膨らませたビーチボールや風船などの内部は多分1気圧より少々高めだが、その力はゴムによって押さえ込まれているはずだ。
定圧の条件はビニール袋以外の方法でも作り出せる。 シリンダーに気体を詰めてピストンを上に置いて塞ぎ、その上におもりを載せておけば、そのおもり次第で気体にかける圧力が調整できるし、この方が体積の測定も容易なので実験にはとても都合がいい。
もしこのピストンにおもりを載せなければ、ピストン自身の重みと外部の気圧がシリンダー内部の気体に掛かっていることになる。 もしピストンの重さが全く無視できる程度で、おもりもなかったとしてもどこまでも膨らんでいってしまうわけではないので安心していい。
実際、ビニール袋やシリンダーなどなくても、そこらに漂っている空気やその他の気体はみんな定圧熱容量で計算できる状態にある。 だからこそ、定圧比熱は重要なのだ。
エンタルピーの導入
このページの上の方を見直してもらいたい。
という関係があるだろう。 この関係を意識しながら次のような新しい量 H を定義する。
これは状態量の組み合わせで作ったものであるから、状態が決まればただ一通りに値が決まる。 つまりこれも新しい状態量である。 エントロピーを発見した時と比べて非常にあっけないが、こんな具合に新しく簡単に作れてしまうような状態量もある。 これが役に立つかどうかが問題だ。
この H の微小変化は
であるが、定圧変化であるという条件のもとでは dp = 0 であり、
となる。 つまりこれは d'Q と同じではないか! d'Q は不完全微分だが dH は完全微分である。 常に状態量でありながら、定圧変化の時に限っては Q と同じ意味になる量、それが H である。
逆に言えば、不完全微分である d'Q は「定圧条件の時には状態量のように振舞う」とも言える。
そもそも不完全微分がなぜ不完全微分であるかと言えば、ある状態へたどり着くのに二通り以上の経路があって、どの経路を通るかによって値が違ってしまうことが原因なのであった。 だから「定圧条件」でも「定積条件」でも「等温条件」でも「断熱条件」でも何でもいいから、とにかく変化の経路を一通りに制限してやりさえすれば不完全微分は状態量としての資格を持つようになるのである。
では何らかの条件の元で d'W と同じ意味になるような新しい状態量も何か考えられるのではないだろうか。 いやいや、あまり期待するものではない。 それはもうすでに出てきている。 第1法則の式をもう一度見直してもらいたい。 d'Q = 0 ならば
ではないか。 つまり断熱条件の元では d'W は状態量のように振舞うのである。 こうして U と H の意外な対称性が見て取れるだろう。
話を戻そう。 この新しい量 H を使えば、定圧熱容量に限っては
と書いてもいいだろう。 H が ( p, T ) の関数であるとすれば、
なので、dp = 0 を考慮して
のように偏微分で書くこともできる。 これで定圧比熱についても
というすっきりした表現を得ることが出来た! しかも Cv と比べても対称的であって気持ちいいではないか。
この便利さを認めて H を「エンタルピー」と名付け、これからも使っていくことにしよう。 語源はエネルギーやエントロピーと同じ作りであり、「en」+「thalp(ギリシャ語で熱の意味)」である。 「内部熱」とでもいったようなニュアンスだろうか? 昔は「含熱量」と訳して使っていたそうだ。 古い教科書ではそうなっている。
エンタルピーの意味
エンタルピーとは何か、と聞かれて、一言で答えられるようなもっと明確なイメージが欲しいものだ。 なぜって、毎年このエンタルピーの意味が理解できずに挫折して行く学生の数の多いことと言ったら・・・。 私もこれにつまづいて、「その先のエントロピーなどはとても理解できるはずがない」と熱力学全体を諦めてしまった口である。
注:エントロピーはエンタルピーの理解とはまるで関係ない。 私の使っていた教科書が前置きも無くいきなりエンタルピーから説明を始めていただけであり、しかもエントロピーの説明の中でエンタルピーという言葉がやたらと使われているので途中からの本線復帰も許されないのだった。
エンタルピーは実はめちゃくちゃ簡単な概念でしかないのだが、簡単すぎるがために不幸を招いている。 先生方は「こんな簡単なものがなぜ分からないのだろう」と首を傾げて、「これならどうだ?」とばかりにさらに難しい説明へと突入してゆく。 学生はそれを聞いて「やはり簡単には説...