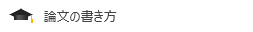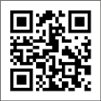資料紹介
状態方程式の微分形
最小限必要な偏微分の知識
全微分形式
理想気体の圧力、体積、温度を結びつける式については前に p V = n R T であるとした。 つまり p, V, T の内の2つの量が決まれば、残りの1つは自動的に決まってしまうということだ。 そこで、体積 V は温度 T と圧力 p の関数 V ( T, p ) であると考えて、次のような式を作ることが出来る。
なぜこのような表現が出来るかについてはきちんと説明しておこう。 軽々しく納得していいところではない。 ・・・とか言いつつも、解析力学のところでやった 以前の説明 はいい加減なものだったが。
温度と圧力がわずかに変化することで、体積がわずかに変化したとする。 その変化は次のように書ける。
これを変形してやれば、
と書けるが、ΔT と Δp について無限小の極限を考えれば、分数で表した部分は微分の定義式そのものである。 ただし高校で習う1変数のみの微分とは少しだけ違っていて、初めの項の中の分数の部分は p の値を固定したままでの T による微分を表しており、2項目の分数の部分は T の値を固定したままでの p による微分になっている。
このように他の変数を固定して行う微分を、通常の微分と区別して「偏微分」と呼び、記号も d の代わりに ∂ を使って区別する。 計算自体は全く難しくない。 考えている以外の変数を定数と見なして微分すればいいだけのことだ。
偏微分を書き表すのに、例えば、
と書いた場合、これは変数 x, y を固定して z で微分することを意味するのだが、もっと簡略化して、
のように固定した変数を右下に書いて表すことがある。 変数が分かっている場合には、右下の変数名さえ省略するし、そうする方が普通なのだが、熱力学ではどの変数を一定に保ったまま状態を変化させるかというところが重要なので、忘れないようにメモ代わりに書いておく習慣になっている。
それで先ほどのような表現が出来ることになるわけだ。 もう一度書いておこう。
・・・ (1)
このような表現を「完全微分」あるいは「全微分」と呼ぶ。 もちろん圧力 p や温度 T についてもそれぞれ p( V, T ) や T( V, p ) であると考えることが出来て、同じように全微分形式で書くことが出来る。
・・・ (2) ・・・ (3)
3通りの表現が出てきたが、どれを使っても本質的には同じ式である。 その時々に応じて一番便利だと思うものを使うことになる。
相関係数
色々な気体の性質の違いを比較するために、実験で p, V, T の間の関係を調べ、幾つかの相関係数として表すことが行われる。 (1) 式が便利な点は、式の中で使われている偏微分係数が、よく使われる相関係数の定義に近い形になっていることである。
例えば、(1) 式の第1項目の偏微分は圧力を一定に保ったまま温度を変化させた時の体積変化を表しているが、これを体積で割ったものは「定圧膨張率」あるいは「熱膨張率」として良く使われる値である。
また第2項目の偏微分を体積で割ったものにマイナスをつけたものは「等温圧縮率」として良く使われる値である。
マイナスが付くだけで難しく見えてしまうが、このマイナスは大した理由ではない。 圧力が増せば体積は減るのでこの偏微分の値は常にマイナスになってしまう。 係数が常にマイナスになるのはかっこ悪いのでそれを防ぐために付けてあるだけだ。
これらの係数を使って (1) 式を
タグ
 All rights reserved.
All rights reserved.
資料の原本内容
状態方程式の微分形
最小限必要な偏微分の知識
全微分形式
理想気体の圧力、体積、温度を結びつける式については前に p V = n R T であるとした。 つまり p, V, T の内の2つの量が決まれば、残りの1つは自動的に決まってしまうということだ。 そこで、体積 V は温度 T と圧力 p の関数 V ( T, p ) であると考えて、次のような式を作ることが出来る。
なぜこのような表現が出来るかについてはきちんと説明しておこう。 軽々しく納得していいところではない。 ・・・とか言いつつも、解析力学のところでやった 以前の説明 はいい加減なものだったが。
温度と圧力がわずかに変化することで、体積がわずかに変化したとする。 その変化は次のように書ける。
これを変形してやれば、
と書けるが、ΔT と Δp について無限小の極限を考えれば、分数で表した部分は微分の定義式そのものである。 ただし高校で習う1変数のみの微分とは少しだけ違っていて、初めの項の中の分数の部分は p の値を固定したままでの T による微分を表しており、2項目の分数の部分は T の値を固定したままでの p による微分になっている。
このように他の変数を固定して行う微分を、通常の微分と区別して「偏微分」と呼び、記号も d の代わりに ∂ を使って区別する。 計算自体は全く難しくない。 考えている以外の変数を定数と見なして微分すればいいだけのことだ。
偏微分を書き表すのに、例えば、
と書いた場合、これは変数 x, y を固定して z で微分することを意味するのだが、もっと簡略化して、
のように固定した変数を右下に書いて表すことがある。 変数が分かっている場合には、右下の変数名さえ省略するし、そうする方が普通なのだが、熱力学ではどの変数を一定に保ったまま状態を変化させるかというところが重要なので、忘れないようにメモ代わりに書いておく習慣になっている。
それで先ほどのような表現が出来ることになるわけだ。 もう一度書いておこう。
・・・ (1)
このような表現を「完全微分」あるいは「全微分」と呼ぶ。 もちろん圧力 p や温度 T についてもそれぞれ p( V, T ) や T( V, p ) であると考えることが出来て、同じように全微分形式で書くことが出来る。
・・・ (2) ・・・ (3)
3通りの表現が出てきたが、どれを使っても本質的には同じ式である。 その時々に応じて一番便利だと思うものを使うことになる。
相関係数
色々な気体の性質の違いを比較するために、実験で p, V, T の間の関係を調べ、幾つかの相関係数として表すことが行われる。 (1) 式が便利な点は、式の中で使われている偏微分係数が、よく使われる相関係数の定義に近い形になっていることである。
例えば、(1) 式の第1項目の偏微分は圧力を一定に保ったまま温度を変化させた時の体積変化を表しているが、これを体積で割ったものは「定圧膨張率」あるいは「熱膨張率」として良く使われる値である。
また第2項目の偏微分を体積で割ったものにマイナスをつけたものは「等温圧縮率」として良く使われる値である。
マイナスが付くだけで難しく見えてしまうが、このマイナスは大した理由ではない。 圧力が増せば体積は減るのでこの偏微分の値は常にマイナスになってしまう。 係数が常にマイナスになるのはかっこ悪いのでそれを防ぐために付けてあるだけだ。
これらの係数を使って (1) 式を次のように表現し直しても良い。
もちろん (2) (3) 式も全く同等な式なのでうまく変形すればこれと全く同じ式に行き着くこともできるわけだが、そのためにはそれぞれの偏微分係数の間にある関係を知らなくてはならない。 それは少し後で説明しよう。
相関係数は他にもあるが、直接的には意味をつかみにくいかも知れない。 例えば先ほど出てきた κ の逆数である「体積弾性率」と呼ばれる量がある。
この定義をいきなり見せられても意味がつかみにくいだろう。 これは結局は圧縮率の逆数に過ぎなくて圧力変化と体積変化の比であるので、同じ事ではあるが
と理解した方が分かりやすい。 これを (2) 式の第1項の偏微分に代入すれば先ほど (1) 式でやったような書き換えができそうだが、話の流れに関係ないのでここではやらない。
(3) 式の第2項にある係数 (∂p/∂T) は温度によって圧力がどう変わるかという意味で「圧力係数」と呼ばれているが、あまり馴染みがないだろう。 これについてはかなり後の方で少しだけ使うことになるかも知れないし、私の説明ではその範囲まで手を出さないかも知れない。
まだ大して深くない内容のところであるにも関わらず、すでに似たような関係式が沢山出て来てしまっている。 熱力学とはこういうものだ。 この先、意味も考えずに片っ端から丸暗記しようとすると非常に効率が悪いことになることは予想が付くだろう。 覚えるべきは式を作り出す手順だけでいい。
理想気体の場合
この微分形式は高校で習うような状態方程式とは比べ物にならないほど便利な表現であって、理想気体以外についても使えるように出来ている。 なぜなら、偏微分係数の値が一定でなければならないという制限がないので、そこは現実に合わせて自由に変化する部分だと考えてやればいいからである。 ずるいやり方だと思うかも知れないが、もっと良く言えば、より柔軟性のある表現になっているわけだ。
すると理想気体の状態方程式というのは (1) 式に含まれる状況の一つに過ぎないということか。 では理想気体のみを表す微分形の状態方程式というのはどんな形をしているのだろう。 確かめておこう。 V = n R T / p を p で偏微分して、
となる。 また V を T で偏微分して、
となる。 これらを (1) 式に代入して形を整えてやれば、理想気体の状態方程式を微分形で表したものが出来上がる。
なかなかすっきりしていて気持ちいい。 しかし、本当にこれでいいのか? モル数を表す n も気体定数 R も消えてしまっているではないか。 確かにこの表現は元の式とは完全に等価というわけではない。 しかし初期条件さえ与えてやれば、この式を積分することで元の式が復元できるのである。 やってみよう。
積分するためには積分範囲を考える必要がある。 ある初期状態 ( p0, V0, T0 ) から始めて、任意の状態 ( p, V, T ) にまで到達することを考えよう。 すると、
と計算できる。 ここで初期状態 ( p0, V0, T0 ) において初期条件 P0V0 = n R T0 が成り立っているとすると、任意の状態で p V = n R T が成り立つことになり、元の式が復元できたことになる。
全微分で表せる条件
上の積分計算で元の式が復元できたのはこれが「全微分形式」だからである。 ところでまだ全微分の本当の意味を話していなかった。 全微分形式で書けるためには条件があって、上の例ではその条件が自動的に満たされていたのだ。
例えば、3つの変数 ( x, y, z ) があって、それらの微小量の間の関係が次のような形で表されているとする。
これを積分して関数 z( x, y ) を求めようとした時、先ほどのように ( x0, y0 ) から出発して ( x, y ) まで進むことを考えるだろう。 もし高校で学ぶような一変数の関数の積分ならば計算の方法は一通りしかないので問題はない。 しかしこの場合は2変数関数になっているために、その計算の道筋は無数に考えられるわけだ。
どういうことかと言えば、例えば、y を y0 に固定したまま x だけ移動して積分を行い、その後で y だけ移動して目標地点に到達することも出来るし、初めに x を固定しておいて y を先に移動して積分することも出来る。 しかしどの道筋を通っても z の値が同じになるなんて保証は何もないのだ。 普通は選んだ経路によって違った値になってしまう。
しかし次の条件を満たしていれば、この積分の結果が一通りに定まることが分かっている。
これは数学の問題なので、ここではその理由を説明はしない。 詳しくは数学の教科書を調べてもらいたい。 ここまで分かっていれば数学も楽しく学べるだろう。
(1) 式はこの条件を満たしていることが分かる。 結局、関数を x と y で偏微分するとき、全ての点でどちらを先にしようとも結果が同じになるようなら問題ないということだ。
熱力学において全微分が大切な意味を持つ理由が分かるだろうか? もし温度や圧力の変化のさせ方の違いによって体積が変わってしまうなら、状態方程式が成り立たないことになるではないか。 変化のさせ方によらずに、ある状態なら必ず同じ値を取るような量を「状態量」と呼ぶ。 全微分の形に書けなければ「状態量」の資格がないわけだ。
全微分の条件を満たさないものは「不完全微分」と呼ばれる。 次回の話でそういう量が出てくることになるだろう。
実在気体の近似式
現実の気体は理想気体の状態方程式に厳密には従わず、少しズレがあるということを前に話したが、次のような「ファンデルワールスの式」は現実の気体についての実験値とかなり良く一致することが知られている。
a と b とはごく小さな値の定数であって、気体の種類によって異なる。 もし a = b = 0 な...