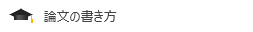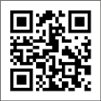資料紹介
 All rights reserved.
All rights reserved.
【ご注意】該当資料の情報及び掲載内容の不法利用、無断転載・配布は著作権法違反となります。
資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )
詩の移行~戦前、戦後、女性~
吉行理恵、高橋新吉、大手拓次の三者の詩を考察するものである。
吉行理恵の「もう だれもいないのに」を読んで
この詩の光景は昔見た覚えがある。母方の親戚に福島の方がいて、昔そこの農家に泊まりに行ったとき、ちょうどこんな景色ではなかったか。当時の私は福島の親戚のおばあちゃんと、その家で飼われていた柴犬と一緒に散歩をしていた。そのときはちょうど嵐の前のような天気で、(雑草ではないが)畑のまだ青々しい稲穂が強めの風に波打っていた。空は灰色の雲に覆われうす暗く、曇天という言葉がしっくりくるような空だ。空気は重く、生あったかい、それでいて私に強くたたきつけるように吹きかかってくる。時間は昼の2時くらいだっただろうか、もっと夕方に近かったかもしれない。大通りなのに人が少なく、前に漫画でみた「世界が終ろうとする直前の風景」に似ていて、どことなく不安な気持ちにさせた。
この詩を読んだときに、「ここまで記憶が鮮明に蘇るものか」と驚いた。しかしながら、この詩の「湯呑み茶わんは独楽のように消えてゆき」や「ひそかに響をあげて畑一面に雑草は靡いていました」などの件は、たしかにその情景...