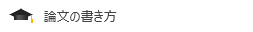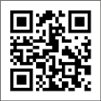資料紹介
法人格否認の法理
最判昭和44 年2 月27 日民集23 巻2 号511 ページXはY会社と店舗の賃貸借契約を締結していた。Yは電器機器販売業をしていたが実質的にはAの個人企業であり、Xは電気屋のAと契約したつもりであった。その後XはAを相手に賃貸家屋の明渡訴訟を提起し、賃貸借契約を解除する和解が成立した。和解に基づきXはAに家屋の明渡しを求めたが、Aは和解の当事者はXAだからAが使用していた部分は明渡すがYが使用している部分は明渡しを拒否した。そこでXがYを相手に提訴した。
「…法人格が全くの形骸にすぎない場合、またはそれが法の適用を回避するために濫用されるが如き場合においては、法人格を認めることは、法人格なるものの本来の目的に照らして許すべからざるものというべきであり、法人格を否認すべきことが要請される場合を生じるのであ。…会社という法的形態の背後に存在する実態たる個人に迫る必要を生じるときは、会社名義でなされた取引であっても、相手方は会社という法人格を否認して恰も法人格がないのと同様、その取引をば背後者たる個人
の行為であると認めて、その責任を追及することを得、そして、また、個人名義でなされた行為であっても、相手方は商法504 条を俟つまでもなく、直ちにその行為を会社の行為であると認め得る…」
→社団法人において、法人格が全くの形骸に過ぎない場合またはそれが法律の適用を回避するために濫用される場合には、その法人格を否認することができる。
 All rights reserved.
All rights reserved.
資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )
法人格否認の法理
1 法人格否認の法理とは、独立の法人格をもつ会社について、その形式的独立性を貫くことが正義
・公平に反すると認められる場合に、特定の法律関係に限って会社の独立性を否定して、会社とその
背後の実体とを同一視する法理をいう。
2(1) では、法人格の独立性を「否認」するとはいかなる場合をいうのか。
(2) そもそも、会社の法人格の独立性とは、会社の対外的活動から生じた権利・義務は法人であ
る会社に帰属し、かつ会社に対して効果が生じる財産法上の行為は会社の機関が行うことにな
り、社員の権限は制約を受けるということを意味する(分離原則)。
つまり、原則として会社と社員とは別...