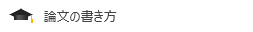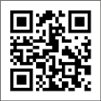資料紹介
内部エネルギー
熱力学の第1法則
熱力学の地位
状態方程式に微積分を応用しただけで随分と高度な学問を扱っているような雰囲気になってきた。 しかし本当にまだ「状態方程式」を触っているに過ぎない。
「熱力学」というからには力に関係があることをやるはずだ。 気体に力を加えた時に熱に関連してどんなことが起こるかを調べるのが熱力学である。 液体や固体については、これらに力を加えても気体ほど大きな体積変化をしないので現象がとらえにくい。 よって今は議論から除外しておこう。
熱現象に限らなければ、気体や液体には「流体力学」という別のアプローチもあるし、固体については力を加えた時の変形具合を議論する「弾性体力学」と呼ばれる分野もある。 熱力学も物質の振る舞いを理解するためのそういったアプローチの一つに過ぎないのだが、統計力学で使う幾つかの概念を提供しているという点で、基礎分野として重要視されている。 統計力学は液体や固体にも適用できるという、それはもう強力な道具なのだ。 そのための基礎作りだと思って取り組んでもらいたい。 たとえ熱力学に限界を見たとしても・・・。
ちょっと伏線
しかし、気体に力を加えたところで全く新しいことが起こるのを期待しない方がいい。 単純な気体の状態というのは ( p, V, T ) のどれか2つを指定すれば完全に定まるのであり、この関係は外から力を加えたところで崩れるものではないからである。 状態方程式はすでに気体の性質をほぼ言い尽くしているのだ。
これからやるのは、状態方程式そのものに手を加える作業ではなく、状態方程式を基礎にして、そこから何が言えるかを調べてゆくという作業である。 状態方程式は単純で、そこから新しいことなど出て来そうも無いと思えるかも知れないが、ぼんやりと眺めていただけでは気付くことのない意外な発見がある。
微小仕事の表し方
さあ、ここからが本題だ。 気体に力を加えよう。 これで気体全体が動く場合は(つまり気体の重心が移動する場合は)、熱力学の出番ではない。 ニュートン力学を普通に使えばいいのだ。 しかし、気体が全体として移動しないでその場で押しつぶされた時には、気体の状態に変化が起こる。
気体をつぶすには、密封できる袋でもピストンつきのシリンダーでもいいが、何かに気体を詰めて、気体の圧力 p に逆らって押す必要がある。 圧力というのは単位面積あたりの力のことであるから、押した面積が S だとすると必要な力は F = pS である。 そしてその力でごく僅かな距離 dx メートルだけ押し込んだとすると、その時に必要となる(ごく僅かな)仕事量は
となる。 面積 S の部分を dx だけへこませたのだから、結局、この気体の体積をごく僅かに dV = S dx だけ縮めたわけだ。 つまり圧力 p の気体の体積を dV だけ変化させた時の仕事量は
と表せることになるだろう。
この時加えた仕事は一体何に使われてどこへ行ってしまったのだろうか。 気体の中に蓄えられたと考えていいだろうか。 そう考えてみることにしよう。
体積が小さくなる(つまり dV が負である)ほど仕事が気体の内部に蓄えられて増える(つまり dW が正である)と考えるのだから、
とマイナスを付けて表しておいた方が都合がいい。 工学では熱力学をエンジンなどに応用するので dW を「気体から取り出す仕事」と考えることが多い。 それでマイナスを付けていない教科書もよく見かけるのだが、最近の物理の教科書ではマイナスを付けることの方が多いよ
タグ
 All rights reserved.
All rights reserved.
資料の原本内容
内部エネルギー
熱力学の第1法則
熱力学の地位
状態方程式に微積分を応用しただけで随分と高度な学問を扱っているような雰囲気になってきた。 しかし本当にまだ「状態方程式」を触っているに過ぎない。
「熱力学」というからには力に関係があることをやるはずだ。 気体に力を加えた時に熱に関連してどんなことが起こるかを調べるのが熱力学である。 液体や固体については、これらに力を加えても気体ほど大きな体積変化をしないので現象がとらえにくい。 よって今は議論から除外しておこう。
熱現象に限らなければ、気体や液体には「流体力学」という別のアプローチもあるし、固体については力を加えた時の変形具合を議論する「弾性体力学」と呼ばれる分野もある。 熱力学も物質の振る舞いを理解するためのそういったアプローチの一つに過ぎないのだが、統計力学で使う幾つかの概念を提供しているという点で、基礎分野として重要視されている。 統計力学は液体や固体にも適用できるという、それはもう強力な道具なのだ。 そのための基礎作りだと思って取り組んでもらいたい。 たとえ熱力学に限界を見たとしても・・・。
ちょっと伏線
しかし、気体に力を加えたところで全く新しいことが起こるのを期待しない方がいい。 単純な気体の状態というのは ( p, V, T ) のどれか2つを指定すれば完全に定まるのであり、この関係は外から力を加えたところで崩れるものではないからである。 状態方程式はすでに気体の性質をほぼ言い尽くしているのだ。
これからやるのは、状態方程式そのものに手を加える作業ではなく、状態方程式を基礎にして、そこから何が言えるかを調べてゆくという作業である。 状態方程式は単純で、そこから新しいことなど出て来そうも無いと思えるかも知れないが、ぼんやりと眺めていただけでは気付くことのない意外な発見がある。
微小仕事の表し方
さあ、ここからが本題だ。 気体に力を加えよう。 これで気体全体が動く場合は(つまり気体の重心が移動する場合は)、熱力学の出番ではない。 ニュートン力学を普通に使えばいいのだ。 しかし、気体が全体として移動しないでその場で押しつぶされた時には、気体の状態に変化が起こる。
気体をつぶすには、密封できる袋でもピストンつきのシリンダーでもいいが、何かに気体を詰めて、気体の圧力 p に逆らって押す必要がある。 圧力というのは単位面積あたりの力のことであるから、押した面積が S だとすると必要な力は F = pS である。 そしてその力でごく僅かな距離 dx メートルだけ押し込んだとすると、その時に必要となる(ごく僅かな)仕事量は
となる。 面積 S の部分を dx だけへこませたのだから、結局、この気体の体積をごく僅かに dV = S dx だけ縮めたわけだ。 つまり圧力 p の気体の体積を dV だけ変化させた時の仕事量は
と表せることになるだろう。
この時加えた仕事は一体何に使われてどこへ行ってしまったのだろうか。 気体の中に蓄えられたと考えていいだろうか。 そう考えてみることにしよう。
体積が小さくなる(つまり dV が負である)ほど仕事が気体の内部に蓄えられて増える(つまり dW が正である)と考えるのだから、
とマイナスを付けて表しておいた方が都合がいい。 工学では熱力学をエンジンなどに応用するので dW を「気体から取り出す仕事」と考えることが多い。 それでマイナスを付けていない教科書もよく見かけるのだが、最近の物理の教科書ではマイナスを付けることの方が多いようだ。
全仕事量の計算
さて、なぜ先ほどからちびちびと微小体積 dV だけ縮めることを考えているのだろう。 理由は簡単だ。 いきなりピストンを押し込むと、押し込んでいる間にも圧力が変化してしまうので、一気に V だけ変化させた時の仕事量を簡単には計算できない。 だからまず dW を計算して、それをちびちびと合計してやるという方法を取る。 つまり積分を使うわけだ。
この積分計算が意味するものを考えよう。 気体の状態を表すのに、 p を縦軸に V を横軸に取ったグラフが良く使われる。
もし理想気体で温度 T が一定ならこれは反比例のグラフになるが、理想気体でない場合には厳密には反比例ではないし、温度が一定でない場合には理想気体であっても変化の仕方に制限は無い。 どんな形の変化でも考えられる。 右上がりだっていいし、くねくね曲がっていてもいい。
気体の状態がグラフ上の A から B まで変化したとしよう。 すると、グラフの赤で示された領域の面積が、その変化の間になされた全仕事量を表していることになる。 とてもイメージしやすいではないか。 逆に B から A まで変化した場合には符号が逆になって、この面積が、気体が外部にした仕事を意味することになる。
準静的過程
この仕事量についての分かりやすいイメージはどんな経路で状態を変化させようとも成り立っているのだが、一つだけ、気体の全体が常に熱平衡を保っているということだけは注意しておいてほしい。
例えばあまりに勢いよくピストンを押すと、気体の内部に圧力の高い部分と低い部分が生まれてしまって、全体として状態方程式が成り立たなくなってしまう。 音速に近い速度でピストンを動かすと、気体の分子運動がそれについて行けずにこのような状況が起こってしまうのである。
ピストンを手でそんなに勢いよく押すことはまず無いだろうが、温度変化についてはもっと注意が必要である。 気体を圧縮すると熱くなるが、シリンダーの外側から順に冷えていって内部に非平衡状態を作り出してしまう。 これを避ける方法はいくつかあるが、例えば、外部に熱が漏れる隙を与えないほど素早く変化させるか、断熱材を使って外部との熱のやり取りをしないようにするか、常にシリンダー内部の全体が外部と同じ温度を保つようにゆっくりゆっくりと外部の温度を調節してゆくか、あるいは、外部の温度を一定に保ったままピストンをゆっくりゆっくり移動させるかしないといけない。 いずれにしても気を使う作業だ。
では平衡状態が保てないような状況では熱力学は全く無力なのだろうか。 例えば、熱平衡が成り立っていると見なせる多数の小部分に分けて、それらの間での熱のやり取りを議論したらどうだろう。 そう甘くはない。 それぞれの小部分の間に温度差がある限り、やはりまた同じ問題にぶつかる。 それを避けるためにさらに小部分に分けて・・・ついには分子の一個一個にまでたどり着くまで続けるといい。 そこまで行くと少数の物理量で全体を表せるという熱力学の利点が意味を成さなくなる。
やはり科学は現実を全て記述できるほど万能ではないというのか。 「非平衡系の熱力学」と呼ばれる分野が昔からあるが、なかなか難しい問題であることが分かる。 近年になってようやく発達してきたようだが、まぁ、コンピュータの助けもなしにそんな計算はしたくないだろう。
前に「熱力学は熱平衡を前提としている」と言ったのはこのことなのである。 熱平衡を保ちながら変化させる過程を「準静的過程」と呼ぶ。 なぜ「準静的」と呼ぶのかと言えば、真の平衡状態では状態は変化しないはずだ。 それが平衡というものだ。 その平衡をほんの少しだけずらすことで徐々に状態を変えて行くのである。 つまり完全に「静的」ではないが、極めて静的に近い変化だと言いたいわけだ。 熱力学はその無限小の変化の極限で成り立つ「理想論」なのである。(注意!ここの表現には重大な問題があることが指摘されています。現在、影響の範囲を調査中です。詳しくは 更新記録 を参照)
これを聞かされるとやる気が失せる人が多い。 まぁ、早い段階で自分が学ぼうとしている理論の限界を把握しておくことは必要だろう。 熱力学自体が熱機関の限界を示すために生まれたようなものなので、その役割は果たしているとは思う。 それに、たとえ現実の全ての状況に適用できなくとも熱力学は結構楽しい。
不完全微分
さて、この気体に蓄えられた仕事量は気体の「状態量」だと考えてもいいだろうか。 そうはいかないのである。 ある状態からある状態へ達するのに、道筋は幾通りもある。 先ほどのグラフを思い浮かべてもらいたいが、仕事 W を表す面積はいくらでも異なるものが考えられるだろう。 前に、経路によって値が異なるものは「不完全微分」であって、状態量としてふさわしくないと話したが、これがそのケースである。
気体を圧縮すると熱くなるが、その状態で放っておくとこの熱は外へ逃げてしまう。 熱が逃げれば温度が下がる。 温度が下がれば圧力が下がる。 圧力が下がった状態で再び体積が増えたとしても、このピストンは外部に対して大した仕事ができない。 気体に蓄えたはずの仕事はどこへ消えてしまったのだろう。
このエネルギーは熱として外へ出て行ってしまって、仕事としては気体の中に残らないのである。 これが仕事を状態量として扱えない理由である。 では熱 Q と仕事 W をひとまとめにして「内部エネルギー」と呼ばれる量を作り、これが気体の中に蓄えられていると考えれば、勝手にどこかへ消えてしまうことがない「状態量」の資格を得るのではないだろうか。 内部エネルギーを U と表せば、その変化は次のように表せる。
熱と仕事が「不完全微分」であることを表すために、 d の後にダッシュをつけて区別してある。 この式が「熱力学の第1法則」と呼ばれるものの数式による表現である。
これは今ではごく当たり前のエネル...