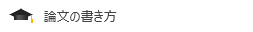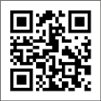資料紹介
R・K・マートン『科学社会学の歩み--エピソードで綴る回想録』サイエンス社、一九八三年、xv + 二五八頁。
訳者あとがき
本書はRobert K. Merton, The Sociology of Science: An Episodic Memoir, Southern Illinois University Press, 1979の全訳である。(ただし、「序文」で著者が述べているように、本書は元来、同じ出版社から一九七七年に刊行されたRobert K. Merton and Jerry Gaston(eds.), The Sociology of Science in Europeの第Ⅰ部として執筆されたものである。)
著者ロバート・K・マートンはアメリカの代表的な社会学者の一人であり、主著『社会理論と社会構造』(みすず書房)の邦訳などを通じて、我が国でも広く知られている。その研究対象は多岐にわたっているが、マートン社会学の出発点が学位論文「十七世紀英国における科学・技術・社会」(一九三八年)にあったこと、すなわち「科学の(歴史)社会学」こそマートン社会学の中核をなしていることは、夙にしられていたが、本回想録はその辺の事情を、一層具体的に明らかにしてくれた。
さて、われわれは本書において、科学社会学という専門分野の歩みを「科学社会学の父」とでもいうべきマートンの眼を通してみることができるわけであるが、本書では言及されていない科学社会学における新しい動向を簡単にみておきたい。
科学社会学の専門としていちはやく産声をあげたのは『科学の社会的研究』Social Studies of Science: An International Review in the Social Dimension of Science and Technologyである。一九八二年で十二巻を数えるこの雑誌は、現在二人の英国の研究者、D・エッジとR・マックロードを中心に編集されているが、プロソポグラフィーや引用分析などを含めて数量的アプローチが重視されていること、さまざまな専門分野-科学者集団の形成をめぐる実証的な研究が多いこと、さらには科学政策的な問題関心が強いことなど、大ざっぱにいって、本書で縷々展開されているマートン流の科学観および科学社会学を踏襲しているとみてよいだろう。
これに対して、一九七七年から年報形式で刊行され始めた『科学社会学年報』Sociology of the Sciences: A Yearbookは、マートン流の科学観および科学社会学を批判し、乗り越えようとする立場から編集がなされているように思われる。というのも、マートンは本書の末尾で、クーンの『科学革命の構造』を曲解したと(マートンがみなす)「鬼子たち」をその相対主義的科学観の故に厳しく断罪しているが、『年報』に依る論者たちは、まさに相対主義的科学観に基づく科学社会学の構築を目指しているからである。たとえば、『年報』は「編集方針」として次のような科学観を呈示している。
本『年報』の基本的な立場は、科学とは自然現象ならびに社会現象を理解するために社会的に構成された複合体である、と考えるところにある。したがって、本『年報』が目指しているのは、諸科学の発展の道を、一つの経過に還元してしまうような、科学知識に関する単一で一面的な図式の克服である。また本『年報』は科学知識の発展に関する研究と科学者に関する研究をあわせて行わねばならないと考えており、さらに社会変革や社会発展をめ
タグ
 All rights reserved.
All rights reserved.
資料の原本内容
R・K・マートン『科学社会学の歩み--エピソードで綴る回想録』サイエンス社、一九八三年、xv + 二五八頁。
訳者あとがき
本書はRobert K. Merton, The Sociology of Science: An Episodic Memoir, Southern Illinois University Press, 1979の全訳である。(ただし、「序文」で著者が述べているように、本書は元来、同じ出版社から一九七七年に刊行されたRobert K. Merton and Jerry Gaston(eds.), The Sociology of Science in Europeの第Ⅰ部として執筆されたものである。)
著者ロバート・K・マートンはアメリカの代表的な社会学者の一人であり、主著『社会理論と社会構造』(みすず書房)の邦訳などを通じて、我が国でも広く知られている。その研究対象は多岐にわたっているが、マートン社会学の出発点が学位論文「十七世紀英国における科学・技術・社会」(一九三八年)にあったこと、すなわち「科学の(歴史)社会学」こそマートン社会学の中核をなしていることは、夙にしられていたが、本回想録はその辺の事情を、一層具体的に明らかにしてくれた。
さて、われわれは本書において、科学社会学という専門分野の歩みを「科学社会学の父」とでもいうべきマートンの眼を通してみることができるわけであるが、本書では言及されていない科学社会学における新しい動向を簡単にみておきたい。
科学社会学の専門としていちはやく産声をあげたのは『科学の社会的研究』Social Studies of Science: An International Review in the Social Dimension of Science and Technologyである。一九八二年で十二巻を数えるこの雑誌は、現在二人の英国の研究者、D・エッジとR・マックロードを中心に編集されているが、プロソポグラフィーや引用分析などを含めて数量的アプローチが重視されていること、さまざまな専門分野-科学者集団の形成をめぐる実証的な研究が多いこと、さらには科学政策的な問題関心が強いことなど、大ざっぱにいって、本書で縷々展開されているマートン流の科学観および科学社会学を踏襲しているとみてよいだろう。
これに対して、一九七七年から年報形式で刊行され始めた『科学社会学年報』Sociology of the Sciences: A Yearbookは、マートン流の科学観および科学社会学を批判し、乗り越えようとする立場から編集がなされているように思われる。というのも、マートンは本書の末尾で、クーンの『科学革命の構造』を曲解したと(マートンがみなす)「鬼子たち」をその相対主義的科学観の故に厳しく断罪しているが、『年報』に依る論者たちは、まさに相対主義的科学観に基づく科学社会学の構築を目指しているからである。たとえば、『年報』は「編集方針」として次のような科学観を呈示している。
本『年報』の基本的な立場は、科学とは自然現象ならびに社会現象を理解するために社会的に構成された複合体である、と考えるところにある。したがって、本『年報』が目指しているのは、諸科学の発展の道を、一つの経過に還元してしまうような、科学知識に関する単一で一面的な図式の克服である。また本『年報』は科学知識の発展に関する研究と科学者に関する研究をあわせて行わねばならないと考えており、さらに社会変革や社会発展をめぐる一般的な研究も重要だと考えている。本『年報』は科学とは、他の生産機構と関連をもつ認識生成機構だとみなしている。したがって、ある特定の認識生成機構が、ある時代に「科学的」なものとして制度化されるに至ったさまざまな過程をめぐる、歴史的かつ比較的な視点からの探求が重要となる。科学知識と常識的な信念・合理性との関連性という論点も、諸科学における認識上の発展の分析にとっては重要であり、本『年報』の課題となろう。(『年報』第一卷、「編集方針」)
じっさい、『年報』の第五卷(一九八一年)は、人類学の視点と手法を踏まえて、科学の相対性-複数性を強調している(E. Mendelsohn an Y. Elkana(eds.), Sciences and Cultures: Anthoropological and Historical Studies of the Sciences--『年報』では多くの場合、複数形の科学sciencesがもちいられていることに注意されたい)。
もっとも、『年報』の諸論文は、しばしば方法論の模索に傾きがちで、編者および寄稿者の意気込みはともかく、少なくとも現在までのところ、具体性・実証性に欠けるという感は否めない。ともあれ、寄稿者のすべてが反マートン主義者とまではいえないまでも、全体として、マートン流の科学観および科学社会学を批判し乗り越えようとして『年報』が編まれていることは間違いのないとことろであろう。
このような『年報』の動きは、他にも波及し、支持を拡げつつあるかにみえる。たとえば、前記『科学の社会的研究』誌も、現代科学をめぐって、相対主義的な科学観に立つ特集号を出した(Social Studies of Science, 11(1981), no.1)。また、科学史研究を科学社会学的視点から概観し、科学史と科学社会学との架橋を目指したS・シェイピンの浩瀚な総説があるが(S. Shapin, "History of Science and Its Sociological Reconstructions", History of Science, 20(1982), 157-211)、これには一五○編近くの著書・論文が言及・紹介されているのに、マートンの論文は一編も挙げられていない。これは、たまたまそうなったというよりも、シェイピンにマートン流の科学社会学克服の意図がある、とみるべきであろう。
しかし、このような反マートン的ともいうべき新しい潮流の存在こそ、科学社会学におけるマートンとその学統を汲む人々の存在の大きさを逆説的に証明しているといえるのではあるまいか--このような状況判断こそ、訳者が、自らは相対主義的=複数主義的科学観に惹かれながらも、あえてマートンの回想録の邦訳に取り組んだ理由である。
右のような「後知恵的理由付け」を別にすると、本書訳出のきっかけになったのは、訳者が「科学社会学研究会」(仮称)に参加して、若い研究仲間から啓発されつつ、科学社会学に対する問題関心を持続させ、発展させることができたことにある。この研究会は、発足以来すでに三年近くになるが、会則に類するものは一切なく、多少なりとも科学社会学に関心をもっている仲間が、数カ月毎に集まって、文献を紹介し、討論し、情報を交換するという、きわめてゆるやかな勉強会である。訳者が、この集まりから得たものは非常に大きい--ということに、学問研究における人間的・社会的結びつきの決定的な重要性を論じた本書(特に第十章「クーンの存在」)を訳出し終えて、あらためて気付かされる。地方大学に在職しているため、研究上の話し相手に恵まれない訳者にとって、東京での研究会を通じて得られる情報と刺激はかけがえもなく貴重なものであったことを、研究会のメンバーに対する感謝を込めて記しておきたい。(この研究会の成果は『科学見直し叢書 全四卷』(木鐸社)、一九八七年-一九九一年、として刊行された。)
回想録という本書の性格を考慮して、訳文・訳語について、訳者なりに工夫をこらして、可能な限り平易になるように努めた。また引用文や専門用語については、すでに邦訳のあるもについてはこれを尊重したが、必ずしもこだわらず、本書の文脈にそくして訳語を選んだ。読者の忌憚のないご批判・ご叱正をまちたい。
大学院時代から現在に至るまで、訳者は村上陽一郎先生から直接・間接に多くのことを学んできたが、その村上先生が多忙なスケジュールの中から貴重な時間を割いて本書に一文を寄せて下さった。もともと科学社会学について、一著を書き下ろすようにとのお薦めをいただいたのに、碩学の手になる価値ある回想録とはいえ翻訳でお茶を濁してしまった不肖の弟子としては御礼の言葉もない。
大谷隆 氏は訳者の願いを了として、粗訳段階で、原文と突き合わせて訳文を検討して下さった。また、脱稿後、荒井克弘、山崎博敏両氏にも訳文・訳語を検討していただいた。おかげで、原文中の難解な個所を読み解く手がかりを与えられたし、多くの誤りや不適当な訳を未然に正すこともできた。また、フランス語およびフランス文学関係については原野昇氏にご教示を乞うた。さらにサイエンス社の橋元淳一郎氏には、原出版社との交渉から校了に至るまで、何から何まで面倒をみていただいた。以上の諸氏に心からの謝意を表する。
翻訳に着手して以来約一年。作業をすすめながら、著者マートンはもとより本書に登場するいく人かの学者たちの豊かな学識や鮮やかな身の処し方と、我が身をひき較べて、忸怩たる思いや暗澹たる気分に何度も落ち込んだが、反面、励まされたり、共感を感じたところも多々あった。ようやく作業を終えて、若干の感慨を禁じない所以である。
最後に、中野好夫氏の言葉を引いて、このやや長すぎた「あとがき」をしめくくりたい。曰く「要するに回想記即自己弁護の書だというのが、私見である。ただそのことを頭においてさえ読めば、これまた回想記ほど興...