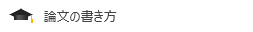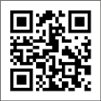資料紹介
伏見憲明 『欲望問題』
「欲望」という言葉に、私はある種の懐かしさを感じる。1980年代後半の、日本のポストモダニズム華やかなりし頃、元ネタはジル・ドゥルーズ、フェリックス・ガタリの『アンチ・オイディプス』か、ジャン・ボードリヤールの消費社会論だったと思うが、いわゆる「ニューアカデミズム」の論壇に一時期あふれかえり、消えた言葉として記憶の片隅に残っていたのが、突如呼び覚まされた気がする。
その時代もアメリカはレーガン・ブッシュ(父)の共和党政権、日本は中曽根政権という布陣だったし、この時期すでに差別糾弾型の人権運動には、一般からは共感よりは猜疑の目が向けられていたわけだから、ちょっとした既視感を感じるのは偶然ではないのだろう。でも、そういった時代背景の相似性よりは、このまだごく近過去といえる時代から今日に至るまで、われわれは当時と異なる視座なり方法論を獲得することに失敗してきたのか、それを見極める素材として、私は本書に惹かれたのだ。すなわち、「クィア」をめぐる言説、これはジェンダーやセクシュアリティに関するポストモダニズムと言い換えてもよい、が、なぜ今まで空回りしてきたのか、ということについての例として。註1 冒頭の一節、「少年愛者の痛み」は感動的ですらある。小児愛者「治療」の推進を説く針間克己医師に対して、かつては同じく治療の対象でしかなかった同性愛者としての立場から、小児を愛する行為を禁止すること自体は正当だとしても、「どこか後ろめたさのような感情が拭えない」と記し、「LGBT(レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー)と総称される運動の当事者に、小児愛者は白々しいほどに想定されていない」という伏見氏の言葉には、アウトローな者への共感があふれている。これは、いわゆる性的マイノリティの中で、政治的にある程度組織できたカテゴリ、あるいはマジョリティに対してある程度の折り合いをつけられたカテゴリは、ある程度社会において顕在化することを許されるし、ある程度権利を主張することもできる。一方、そこから外れる者は、逆にアウトロー化される結果を招くような「運動」に対する、つとめて反省的な態度表明のようにも読める。 しかし、伏見氏はジェンダーについては一転、態度を翻す。「欲望」はジェンダー・カテゴリが存在することに*よって*生まれるのであり、ジェンダーを無くすことを指向する「ジェンダーフリー」運動を「不可解」であると切り捨てる。そして、伏見氏はジェンダーフリーにまつわる混乱を、「理論と生活感覚の摩擦」であるとし、後者をほぼ無条件に肯定する態度に出る。すなわち、ジェンダーを無くすことは恋愛やファッションや芸術を一切無くすことであるとする。 なるほど、ステレオタイプ化されたジェンダーフリー論を根拠にすれば、そういう結論も可能である。しかし、性愛はジェンダー・カテゴリによって*のみ*生まれるわけではない。前述少年愛についてもそうであるが、SMやさまざまなフェティシズムを例にあげるまでもなく、ジェンダーによらない性愛はいくらでもある。多様なジェンダーやセクシュアリティが抑圧されることなく、その存在を肯定されるには、異性愛だけが奨励され、二元的な性別観だけが奨励される「生活感覚」を、いくらかでも改める必要がある。伏見氏はなぜジェンダーに関しては矛盾した態度をとるのであろうか。註2 同様の議論は、ゲイ・アイデンティティをめぐっても展開される。伏見氏は、初期の頃は「ゲイというカテゴリ化からの解放が望ましいと考えていました」と語る。しかし、現時点ではそ
タグ
 All rights reserved.
All rights reserved.
資料の原本内容
伏見憲明 『欲望問題』
「欲望」という言葉に、私はある種の懐かしさを感じる。1980年代後半の、日本のポストモダニズム華やかなりし頃、元ネタはジル・ドゥルーズ、フェリックス・ガタリの『アンチ・オイディプス』か、ジャン・ボードリヤールの消費社会論だったと思うが、いわゆる「ニューアカデミズム」の論壇に一時期あふれかえり、消えた言葉として記憶の片隅に残っていたのが、突如呼び覚まされた気がする。
その時代もアメリカはレーガン・ブッシュ(父)の共和党政権、日本は中曽根政権という布陣だったし、この時期すでに差別糾弾型の人権運動には、一般からは共感よりは猜疑の目が向けられていたわけだから、ちょっとした既視感を感じるのは偶然ではないのだろう。でも、そういった時代背景の相似性よりは、このまだごく近過去といえる時代から今日に至るまで、われわれは当時と異なる視座なり方法論を獲得することに失敗してきたのか、それを見極める素材として、私は本書に惹かれたのだ。すなわち、「クィア」をめぐる言説、これはジェンダーやセクシュアリティに関するポストモダニズムと言い換えてもよい、が、なぜ今まで空回りしてきたのか、ということについての例として。註1 冒頭の一節、「少年愛者の痛み」は感動的ですらある。小児愛者「治療」の推進を説く針間克己医師に対して、かつては同じく治療の対象でしかなかった同性愛者としての立場から、小児を愛する行為を禁止すること自体は正当だとしても、「どこか後ろめたさのような感情が拭えない」と記し、「LGBT(レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー)と総称される運動の当事者に、小児愛者は白々しいほどに想定されていない」という伏見氏の言葉には、アウトローな者への共感があふれている。これは、いわゆる性的マイノリティの中で、政治的にある程度組織できたカテゴリ、あるいはマジョリティに対してある程度の折り合いをつけられたカテゴリは、ある程度社会において顕在化することを許されるし、ある程度権利を主張することもできる。一方、そこから外れる者は、逆にアウトロー化される結果を招くような「運動」に対する、つとめて反省的な態度表明のようにも読める。 しかし、伏見氏はジェンダーについては一転、態度を翻す。「欲望」はジェンダー・カテゴリが存在することに*よって*生まれるのであり、ジェンダーを無くすことを指向する「ジェンダーフリー」運動を「不可解」であると切り捨てる。そして、伏見氏はジェンダーフリーにまつわる混乱を、「理論と生活感覚の摩擦」であるとし、後者をほぼ無条件に肯定する態度に出る。すなわち、ジェンダーを無くすことは恋愛やファッションや芸術を一切無くすことであるとする。 なるほど、ステレオタイプ化されたジェンダーフリー論を根拠にすれば、そういう結論も可能である。しかし、性愛はジェンダー・カテゴリによって*のみ*生まれるわけではない。前述少年愛についてもそうであるが、SMやさまざまなフェティシズムを例にあげるまでもなく、ジェンダーによらない性愛はいくらでもある。多様なジェンダーやセクシュアリティが抑圧されることなく、その存在を肯定されるには、異性愛だけが奨励され、二元的な性別観だけが奨励される「生活感覚」を、いくらかでも改める必要がある。伏見氏はなぜジェンダーに関しては矛盾した態度をとるのであろうか。註2 同様の議論は、ゲイ・アイデンティティをめぐっても展開される。伏見氏は、初期の頃は「ゲイというカテゴリ化からの解放が望ましいと考えていました」と語る。しかし、現時点ではその立場を否定し、「ライフスタイルを共有する者たちの共同性」として、アイデンティティを再構築する立場に立つことを表明する。会員制サイトmixiなどに、ゲイというカテゴリが必要不可欠でもないのに、「歌手の○○が好きなゲイ」といったコミュニティが林立していることを例にあげる。 そこに被差別体験を共有する者による政治という意味でのアイデンティティ政治は想定されていない。そうではなく、快楽を共有する者によるアイデンティティ政治が目論まれている。しかし、そのアイデンティティが排他的な帰属のメルクマールであることには変わりはない。言い換えれば、同じ「欲望」をもつもののうち、それを認められる者と認められない者を自主的に選別する基準であるという点では、旧来のアイデンティティ政治のそれと異なるところはない。 もちろん、伏見氏のジェンダー擁護的な態度には、ゲイやレズビアンというカテゴリが、男性または女性というカテゴリを前提に成立していること(あるいはそれゆえ二元的な性別観に疑いをもたないこと)に原因を求めることもできよう。しかし、クィア・ムーブメントの初期に影響力のある立場にあった伏見氏が、ゲイやレズビアンがセクシュアリティだけでなく、オネエやブルダイクのように典型からかけはなれるジェンダー表現のために抑圧を受けてきたことを意識していないわけがないだろう。伏見氏が新たにカテゴリとアイデンティティの基準として価値を見出す「ライフスタイルの共有」を持ち出すのには、他の意図がある。 tummygirl氏 は、本書『欲望問題』とネオリベラリズムの関連を指摘している。 tummygirl氏は、「非規範的セクシュアリティの承認要求がネオリベラリズム的な脱「政治」化要請との親和性を持つのではないか」と指摘している。もともと、1980年代においても、性的欲求と消費欲を関連付ける用法としての「欲望」という用語は、当時のバブル経済における消費社会論におけるバズ・ワードであった。宗教的規範が比較的弱い日本においては、ゲイに対する社会的理解を得る障壁は諸外国ほどではないし、男性としての経済的特権は、ゲイであることを隠す限りで享有できる。欲望と快楽に身をまかせて、消費を楽しむライフスタイルを確立する基準として、アイデンティティを想定することはありうる。 ある程度反差別運動が成果をむすび、マイノリティとされるカテゴリの中にも経済力をつけ、指導的な地位につく者がでてくるフェーズにおいては、もはや差別は終わった、あとは個人の努力次第という言説が必ず現れる。フェミニズムにおいても、ポスト・フェミニズムの名のもとに、フェミニズムが一定の成果を獲得したという認識の上に、運動としてのフェミニズムからの自由が主張されたことがある。確かに、このようなフェーズにおいては、旧来の「差別」が実感されにくくなるのは事実である。そのような環境の中では、否定的な「差別」でなく肯定的な「欲望」に目を向ける方が、支持者の数という点では稼げるのは確かである。 しかし、この「欲望」を実現できる人と十分に実現できない人の格差はなお存在する。階級や職業、地域、人種、障害、家庭環境等によって、いまだ「痛み」を伴う差別を受ける人はなくならない。むしろ、伏見氏に必要とされた態度は、このような*それぞれの*「欲望」に耳を傾けることではなかったのではないか。そして、マジョリティの「生活感覚」と異なるクィアの「生活感覚」を再構成し、マジョリティに対しても再提示することではなかったか。さらには、いわゆる当事者にも巧妙に内面化される「制度」に気付きをあたえ、それをからかいもてあそぶキャンプの精神を、推し進めることではなかったのだろうか。これらの方向を見失ったように見えるのは、本書において「欲望」と消費社会、さらにその背後にあるネオリベラリズムの関係、さらにはその格差性が十分に解き明かされないままだからである。 伏見氏は日本に「クィア」という用語を導入した先駆者の一人であったし、それゆえにクィア=ゲイ(男性同性愛者)と誤解されることも多かったが、旧来のアイデンティティ政治にこだわらず、それとは異なる手法を模索していた点においては、今日に至るまで一貫している。しかし、本書には、これまでの批判の対象や活動の目標を見失ったがゆえの迷いが感じられる。伏見氏には、それこそ「命がけ」で、クィアのありかたを再考してもらいたいと、一読者ながら思う。
註1 アセクシュアルの立場から見れば、そもそもすべてを「欲望」の問題に還元すること自体が、しばしば伏見氏を含む同性愛者が陥りがちな性欲中心主義の結果でしかないのではないか、という指摘が可能であるが、ここでは傍論にとどめたい。 註2 ジェンダーなきセックスを提唱するケイト・ボーンスタインと、ジェンダーはセクシュアリティの根拠であるとしてボーンスタインを批判するパトリック・カリフィアの間にも、類似の論争が存在した。Kate Bornstein, Gender Outlaw, Patrick Califia, Sex Changes参照。
伏見憲明 『欲望問題』 ポット出版、2007年 ISBN978-4-7808-0000-5
資料提供先→ http://homepage2.nifty.com/mtforum/br007.htm