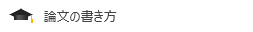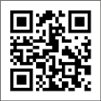資料紹介
 All rights reserved.
All rights reserved.
資料の原本内容
「法における人間」を読み解く
法における人間について論じるにあたり、法は自らが働きかけようとしている人間をどのように捉えているか、つまり、法とはどのような種類の人間に向けられたものなのか、ということをテーマとしている。すなわち、現実の人間ではなく、法の念頭におかれ、そして法が命令を向けているところの人間像をテーマとしているのである。
法規は、その普遍性ゆえに、もっぱら人間の一般的類型を対象として作られている。そして、それぞれに異なった人間の特性が、それぞれの法時代にとって、法的規制のための基準的な出発点として登場してくるのである。
法秩序にとって、権利の尊重は、その重要さの点において、なんら義務の履行に劣るものではない。イェーリングによれば、単にその義務がもはや履行されないときだけではなく、その権利がもはや主張されないときにおいても、法秩序は崩壊せざるを得ないとしている。法秩序は、その意思の実現を期待できると考える場合には権利を与え、自らの希望と逆行する衝動に対して、反対動機を設定しなければならないと信じる場合には義務を課するのである。したがって法秩序は、法秩序によって設定された権利と義務とを通じて、法秩序自身が、人間の中にはどのような衝動が存在し、かつ働いていると考えているか、ということを示している。
法時代にとって特徴的と思われるのは、義務によって支えられた権利、つまり義務に適ったように行使されるという期待のもとに認められた権利が通例であったという点である。このような権利は、安全にその機能を果たすためには、習俗とか宗教を通じて、義務及び共同体に結び付けられた人間を前提としている。
ツンフト制度とは、ツンフトの名誉は優秀品を供給するための十分な要因となるであろうという信頼のもとに認められた独占を意味していた。この信頼は、数世紀にわたって実証された。
レーンの制度とは、レーンに対する忠誠の精神においてこれを行使するという、ほとんど監督することも強制することもできない条件のもとに、きわめて広汎な権利が与えられていたことを意味した。しかし、この条件は役に立つことはなく、法における人間観がしだいに時代とそぐわなくなっていったのである。
ルネッサンス・宗教改革・ローマ法継受は、義務によってではなく、利益によって導かれた個人というものを法の出発点にした。新しい人間関係は、利潤関係と打算に終始する商人像を模してつくりあげられた。したがって、それ以来、法はすべての人を商人と同視しており、労働者さえも「労働」という商品の売り手としてみているのである。
利己主義の元における法時代は、警察国家と啓蒙とに分けられる。警察国家は、その臣民の当然の後見人であり、彼らが自己の家政をいかに整えるべきかを彼らの意思に反しても教示しようとするものである。したがって、打算された利己主義が同じ目的を持っていたとしても、権利だけでなく、むしろ義務が設定されるのである。
人間類型に基づいた法制度を啓蒙と自然法とが整備するに至ったことで、マキァヴェリも「人間が悪しきものとして前提しないにおいては、何人といえども、共和国に憲法とか法律をもたらすことはできない」と言っているように、法律は、きわめて利己的にして狡猾きわまる人間という仮定的な構成を対象とし、かつ、かかるものについて自らをためさなければならないのである。しかし、かの法時代にとっては、このような人間類型はたんなる仮定的構成以上のもの、すなわち経験的な平均的類型であったのだ。
新しい人間類型にもとづいて全法秩序をつくりあげたことで、義務にしたがって行使するという、見せかけだけの条件のもとに与えられていた、かの一切の権利は、独自の権利と独自の義務とに解体される。そこでは、利益とそれを実現するための手段とを、法的手段をも含め、認識しかつ実効に移すだけの怜悧さと積極性とが前提とされている。打算された利益の追求を妨げる、法そのものによって設けられたもの以外のすべては無視され、法形式的な契約自由は、現実の契約自由とみなされるのである。利己的、知性的、活動的で自由なものであると考えられた人間は、たがいに平等なものと考えられたのである。
アンゼルム・フォイエルバッハの心理強制説は、刑法において、いっさいの本能や良心からの負担もなく、純粋に利己的かつ合理的に、その企てた犯罪がもたらす快・不快の結果の計算を試みた上で、その打算された利益を追求しようとする人間を前提としている。後者もまた、社会契約説において、自由にして平等な人間の打算された個人的利益によって基礎づけられ、かつ、支えられているものとしてとらえられている。ルソーは、政党の形成は個人的利益の表明を誤るという理由から、これに対して反対したのであったが、過去の国家学および国法学も、それにかかわらず強力に発展した政党を、少なくとも無視していた。政党は、法的な権威を持たない純然たる社会学的存在と考えられ、法にとっては、個々の選挙民が存在したにとどまるのである。法は、あらゆるその領域において、個人的主義的、主知主義的な人間類型に向けられており、例えば家族法では、その妻および子に対する関係において、これまでのようにそれが義務にしたがって行使されるという期待のもとに、夫と父に権利が託されてよいと考えていたのである。しかし、次第に夫権および親権を義務にしたがって行使するための法的な保障が採り入れられてきたのである。
オーストリア民事訴訟法[一八九五年]において、当事者の自由な合同遊戯に対し、当事者の利益のために裁判官が補助的かつ指導的に介入しており、弁論主義は次第に打破されている。犯罪者に対して必要なのは、彼らを改善することであり、せめて何が自己自身の利益であるかを理解し、その利己的な利益にしたがって行動するように、彼らを高めてやることであると解された。そしてその改善思想は、単一の行為者類型を越え、多様な心理学的類型を、法律的にも意味あるものとして着目させるに至っており、こうした新しい刑法理論は、それがこれまではただ一連の社会学的事実にすぎなかったものを法律的に意味あるものにまで高めている点で、まさに社会学的刑法理論とよばれて然るべきである。
新しい人間像は、生活に密着した類型であり、権利主体の知的・経済的・社会的な勢力関係というものをあわせ考慮されている。法における人間とは、孤立した個人ではなく、集合人――つまり、社会の中で生きる人間のことなのである。しかし、法律的人間類型が社会的現実へと接近してゆくにつれて、権利主体もまた、社会的な、法律的に意味ある多数の類型へと分裂してゆく。これは特に労働法に顕著である。
市民法が知っているのは、相互に自由なる決定に基づいて契約を締結する平等な権利主体のみであって、企業主に対し、その劣勢な地位においてとらえられた労働者ではない。要するに、企業というものの団体的一体性について何も知らないのであり、市民法が見ることができるのは、たがいに何ら法的な紐帯によって結合されていない被傭者達と同一の使用者との間の多数の労働契約のみであって、完結的な社会学的単位としての従業員団体ではない。それは、自由なる契約のみでなく、そうした見せかけの自由契約の背景を成している熾烈な経済的権力闘争なのである。
我々にとって民主主義とは、「人間にとって全ての平等」ではなく、既に「指導者選出」の最善の方法を意味しており、孤立化した個人の上に築かれた民主主義が、集合人の概念という観点から考えなおされている。法における人間を集合人として考えるということは、新たに倫理的な義務内容を権利に盛るということである。イェーリングは、「所有権は義務を伴う」「選挙権は選挙義務である」等、権利のための闘争を倫理的な義務にまで高めている。かかる権利の義務浸透性ということによって、我々にとっても、すべての権利は全体からの単なる貸与と考えられている。この義務浸透性は、社会的法時代にとって、家長的法時代とは異なり、義務による被拘束性でもある。
法秩序の客体としての種々の人間観について必要なのは、法はいったい人間たる立法者をその創造者として考えているか否か、ということを素描することである。ゲルマン古代にとって、法・習俗・倫理・宗教は一つのものであって、法は同時に祖先の英知、民族の良心の声、神々の意思であるため、人間による立法から避けられていた。それゆえ、最初の立法者は、汚れた手をもって神々の大権を冒涜した人間として考えられざるをえなかったのである。
近代をずっと下った頃までも、まだ法律学と法実務は、たんに法律を引きあいに出すだけでなく、法律を強化するために他のいろいろな権威、すなわち聖書や古典を引きあいに出すことを常としていた。その内容の正しさにしたがって効果を認めようとする、自然法の時代にあるのである。ホッブズでさえ、「法は助言するものではなくて、命令するものである」と、繰り返し強調せざるを得なかった。
ローマ法の継受が、国家意思に対して制定法としての効力をもたらしめ、その効力を実施にうつしたのは絶対国家だった。ここで初めて啓蒙が、民族精神の衝動的意欲を国家的立法者の目的的意思によって置き換えたのである。そこで、一挙にして、現代の法律用語が存在するにいたった。ついに、絶対的支配者という形において、人間が立法者として歴史に登場したのである。
絶対国家から立法国家への発展は、国家意思のなかへ民衆意思が採り入れられたということ、法が改めて非人格化されかつ共同体化されたことを意味する。立法はもはや、ひとり国民代表のみ...