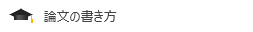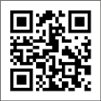資料紹介
 All rights reserved.
All rights reserved.
資料の原本内容
第2課題
Aは暴力団組長であるが、けん銃を所持する子分B、C2人のボディガードに常時警護されていた。某日、車で走行中警察官に停止を求められ、捜索差押許可状による捜索差押えを受け、B、Cはけん銃を押収され、銃砲刀剣類所持等取締法3条違反で現行犯逮捕された。B、Cが警護のため常時けん銃を所持していたことをAは概括的とはいえ確定的に認識しており、そのような警護をむしろ当然のこととして受け入れ、認容し、B、CもAのこのような意思を察していた。A、B、Cの刑事責任について論ぜよ。
第3課題
Aは、殺人の故意でBに対して発砲したところ、弾はBの肩を貫通し、Bに障害を負わせ、さらにたまたま通りかかったCに命中し、Cを死亡させた。Aの罪責を論ぜよ。
第2課題
1.刑法60条は、犯罪実行行為の一部のみを担当した者も正犯とする旨規定しており、本問において、AがB、Cの銃砲刀剣類所持等取締法3条違反につき、その行為の一部を担当している正犯といえるかどうかが問題となる。
2. 共謀共同正犯
一部のみを担当した者も当該犯罪全体について刑事責任を負うこと(一部実行・全部責任の原則)が認められる根拠は以下のように考えられる。
①二人以上の者が、共同実行の意思に支えられ、特定の犯罪実現に向けて共同するという相互利用補充関係によって法益侵害の危険性が増大し、②一部のみを担当した者は共謀に基づき、他者の行為を通じて自己の犯意を実現しているからである。
そのように考えると、共同者は必ずしも実行行為の一部を現実に分担する必要はなく、二人以上の者が共同意思のもとに相互に利用・補完しあって、実行行為が行われれば足りると解すべきである。けだし、正犯として重要な役割を果たせば、必ずしも実行行為を行う必要はなく、実行行為が共同意思に基づくという意思方向をもてばよいし、強い因果性を根拠に、実行行為の一部をも行わなかった者に客観的行為を帰責することは十分可能であるからである。また、「共同して犯罪を実行した」とは、共同した者のうちいずれかが犯罪を実行した場合ないし実行行為が共同のものと評価できる場合と読むことも可能である。
よって、主体的に犯罪の謀議に参与したが、当該犯罪の実行に及んでいない場合であっても、共謀を通じて犯罪実行行為に影響力を与えていることで正犯となる(共謀共同正犯)。
この考えは、判例(最大判昭33・5・28刑集12巻8号1718頁等)・通説によって肯定されている。
3.共謀共同正犯の成立要件
共謀共同正犯が成立するためには、①共同して犯罪を実行する意思のもとに、②相互に他人の行為を利用して各自の意思を実行に移す謀議をなし、③共謀者のある者がその犯罪を実行することを要する。
(1)共同意思とは、相互に他人の行為を利用補充しあって犯罪を実行する意思をいい、教唆の意思ないし幇助の意思では足りず、正犯者の意思であることが必要である。
(2)共謀とは、二人以上の者が特定の犯罪を行うために相互に他人の行為を利用し補充しあい、各自の犯意を実行に移すことを内容とする謀議を行い、合意に達することをいう。したがって、単に共同実行の認識があるだけでは足りず、犯罪を他の関与者と協力し合って遂行するという共同実行の意思が必要である。
(3)少なくとも共謀者の一人が、共謀に基づいて実行行為を行うことが必要である。
4.黙示の共謀
共謀共同正犯における最重要要件は共謀であるが、明示的な共謀が存在していなくても、共謀共同正犯が成立するかどうかが問題となる。
現場共謀については、黙示の共謀があったとして、共謀共同正犯を認めることができるであろう。
これに対して、事前共謀であって、実行行為に全く加わっていない者に対して共謀共同正犯として罪責を負わせることには消極説も多いが、判例(最決平成15・5・1刑集57巻5号507頁)は、これを肯定する。
「被告人は、スワットらに対してけん銃等を携行して警護するように直接指示を下さなくても、スワットらが自発的に被告人を警護するために本件けん銃等を所持していることを確定的に認識しながら、それを当然のこととして受け入れて認容していたものであり、そのことをスワットらも承知していた……前記の事実関係によれば、被告人とスワットらとの間にけん銃等の所持につき黙示的に意思の連絡があったといえる。そして、スワットらは被告人の警護のために本件けん銃等を所持しながら終始被告人の近辺にいて被告人と行動を共にしていたものであり、彼らを指揮命令する権限を有する被告人の地位と彼らによって警護を受けるという被告人の立場を併せ考えれば、実質的には、正に被告人がスワットらに本件けん銃等を所持させていたと評し得るのである。」とした。
しかしながら、共謀が黙示的意思連絡で足りるとするのは、共謀共同正犯の成立範囲を拡大するもので容認できないと考える。
5.結論
以上より、本問において、B、Cが警護のため常時けん銃を所持していたことをAは概括的とはいえ確定的に認識しており、そのような警護をむしろ当然のこととして受け入れ、認容し、B、CもAのこのような意思を察しているとしても、そこにはけん銃を所持して警護することへの黙認が存在するだけで、共謀があったとみることはできないから、共謀共同正犯は成立し得ない。
立石二六『刑法総論[第3版]』285頁以下、(成文堂、2009年).
伊藤真『伊藤真の刑法入門[第3版]』369頁以下、(日本評論社、2007年)
第3課題
1.刑法38条1項は、故意があることを犯罪成立要件としている。本問において、Aが当初意図していたBとは異なる客体であるCを死亡させた点につき、「故意あり」といえるかどうかが問題となる。
2.事実の錯誤
事実の錯誤とは、行為者が行為当時認識・認容していた犯罪事実と現実に発生した犯罪とが一致しない場合をいう。
事実の錯誤がある場合において、当初犯人がもっていた故意を発生した犯罪事実に対する故意と法的に評価できるのかが問題となる。
(1)具体的符合説
表象事実と発生事実とが具体的に符合したか否かを基準とする。方法の錯誤の場合には、両者が具体的に符合すれば故意既遂を認め、符合しなければ、表象事実については未遂、発生事実については過失を認めその観念的競合とする。他方、客体の錯誤の場合には、意図した対象に結果が生じているから故意既遂を認める。
(2)法定的符合説
行為者の表象した事実と発生した結果が同一構成要件内で符合しているので、認識内容と異なる客体に対する故意を認める。具体的事実の錯誤の場合には、客体の錯誤、方法の錯誤、双方について故意既遂を認め、他方、抽象的事実の錯誤の場合には、表象事実について未遂、発生事実について過失の成立を認めその観念的競合とするが、その際、同質的で重なり合う構成要件間の錯誤については、重なり合う限度で軽い罪の故意を認める。
(3)私見
具体的符合説は、方法の錯誤と客体の錯誤でその取扱を異にする点で一貫性がなく、表象事実と発生事実とが具体的に符合しない以上、客体の錯誤の場合にでも、既遂ではなく、未遂と過失の観念的競合を認めることが妥当である。また、方法の錯誤において、未遂も過失も処罰されていない場合に処罰の間隙が生じるという問題もある。
法定的符合説においても、抽象的事実の錯誤において、表象事実について未遂、発生事実についての過失の処罰規定が存在しないときには不処罰になるという解釈論上の欠陥がある。しかし、それは立法により解決されるべき問題であるし、解釈によって処罰するということも罪刑法定主義の見地において許容されると考える。
よって、法定的符合説を支持する。
3.一所為一故意の原則
一所為一故意の原則とは、行為者が特に別個の故意をもっていない限り、一個の行為には一個の意思しか存在しないという原則である。
法定的符合説を取り得るとしても、故意の個数が問題となる。
(1)数故意犯説
故意は構成要件の範囲で抽象化されるので、故意の個数を観念する余地はなく、発生した結果の数だけ犯罪が成立しても、観念的競合(54条1項前段)として処理されるので不合理ではない。
よって、発生した犯罪事実の個数分の故意犯の成立を認める。
(2)一故意犯説
1個の故意については、1個の故意犯を認めるのでなければ、責任主義に反することとなるから、発生した犯罪事実のうちもっとも重い結果に対し、1個の故意犯の成立を認めれば足り、それ以外の結果に対しては、原則として過失犯の成立を認める。
(3)私見
一所為一故意の原則を貫徹する一故意犯説が妥当と考える。
5.結論
以上より、本問において、Aの殺人の故意とCの死亡という結果が同一構成要件内で符合しているので、Cに対する故意が認められ、殺人既遂罪が成立し得る。また、Aは、殺人の故意でBに障害を負わせているから、Bに対しても殺人未遂罪が成立し得る。
しかし、一所為一故意の原則より、故意は1個に限定されなければならないから、Bに対する殺人未遂とCに対する過失致死の観念的競合を認めるのが妥当である。けだし、Bに対する過失致傷罪とCに対する殺人既遂罪との観念的競合を認めると、殺害の故意が向けられた相手に現実に傷害結果が生じているのにこれを過失致傷と解することには疑義が生じるからである。また、錯誤論から故意論を導くのではなく、故意論の欠陥なり不足なりを補足・補完するところに錯誤論の意味があると考えるべきであるからである。
立石二六『刑法総論[第3版]』194頁以下、(成文堂、2009年).
伊藤真『伊藤真の刑法入...